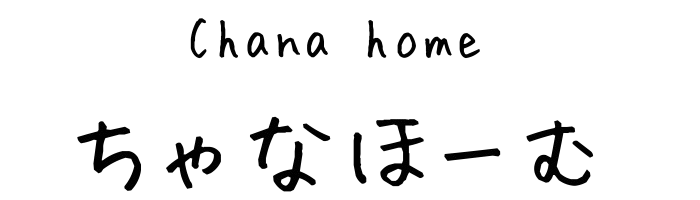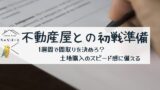土地の購入申込みの後は何が起きるの?お金もどの位払うのかな…

申し込みから引き渡しまで意外と細かいステップがあるよ。でも大枠の流れを整理すれば不安は減るから、大丈夫だよ
こんにちは。
今日は、先日の土地抽選会にて縁のあった土地の購入申込書を提出してきました。
そして、申込金として10万円を現金で支払いました😣
マイホーム計画を始めてからこれが初めての現金の支出です。
「マイホーム構想から8年、土地探しから2年、ついにここまで来たのか」と、少し感慨深い気持ちになりました😀
「土地の申し込みって何を準備すればいいの?」「契約後にやることが多すぎて不安…」
私も当初そんな気持ちを抱えながら家づくりを進めてきました。
この記事では、分譲地の購入を進めている一施主として、
申し込み〜契約〜引き渡しに至るまでの具体的な流れや費用を整理しています。
これから土地を購入しようとしている方や、申込み後の流れに不安を感じている方にとって、「次に何をすればいいか」がわかる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。


この記事を読んで分かること
- 土地購入の流れ(申し込み〜契約〜引き渡し)
- 分譲地購入時の申込金や契約金の金額と支払タイミング
- 所有権移転登記にかかる費用の内訳と相場
- 固定資産税評価額の求め方と実例
- 抵当権設定登記にかかるおおよその費用
土地購入までの流れは大きく3ステップ


不動産会社から説明を受けた内容によると、今後の土地購入までの手順は、次のような3ステップに分かれていました。
【ステップ①】購入申し込み ※本日完了
- 分譲地購入申込書の記入
→ その場で用紙を受け取り、内容を記入して押印。 - 申込金:10万円の支払い
→ 現金で支払いました。
→ もしキャンセルする場合は全額返金されるとのことです。 - 必要書類の受け取り
→求積図(座標の記された土地の図面)、土地の平面図などの図面。
→預かり証、物件概要、今後の予定表などの書類。
【ステップ②】土地売買契約(1か月以内に実施予定)
次回の契約時に必要な持ち物は以下の通りです。
- 土地価格の5%の手付金
(例:2,000万円の土地なら100万円ですが今回は40万円で良いとの事😲) - 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印でも可、可能であれば実印)
- 収入印紙:1万円分(郵便局などで事前購入)
【ステップ②でやること】
- 重要事項説明書の読み合わせと確認
- 不動産売買契約書の締結
これらの手続きは不動産会社の事務所で行われ、所要時間は1時間半程度とのことでした。
まあまあ長い時間ですが不動産屋によるとあっという間に終わるそうです😣
重要事項説明書・契約書に関する確認事項
これらの書類に関しては過去にトラブルになったという事例もよく耳にしていたため、以下の3点について、担当の方に事前に確認しました。
Q1:契約前に「重要事項説明書」と「売買契約書」をもらうことはできますか?
A1:可能です。契約の約1週間前には送付可能です。
Q2:「重要事項説明書」や「売買契約書」は、国土交通省や宅建協会が提供している書式に基づいて作られているのですか?
A2:はい、基本的にはその雛形を使っています。ただし、一部内容に変更が加えられている場合があります。
Q3:雛形からの変更箇所を明示してもらうことは可能ですか?
A3:明示はできませんが、変更された箇所はすべて「不動産会社にとって制限が強まる方向」の変更であり、購入者にとって不利になるような変更はできない仕組みになっています。。
このあたりのやり取りや注意点については、後日あらためて別の記事でまとめる予定です。
もしよろしければ、このブログをブックマークしておいていただけると嬉しいです。
【ステップ③】土地の引き渡しと残金決済(住宅ローンの実行)
最後のステップは土地の引き渡しと住宅ローンの実行(残金決済)です。
通常、このステップ②の契約から③の引き渡しまでの期間は、おおむね2か月以内とされています。
その間に、住宅ローンの本審査を通す必要があります。
本審査を通すには、住宅会社の決定と、建物請負契約書・建物費用の明細書の提出が必須です。
つまり、この2か月の間に間取りや仕様を決定しなければならない、ということになります😱
「2か月で仕様まで決めるなんて無理なのでは…?」
正直、私もそう思っていました。
これらの心配に対する対策はこの記事を参照ください。
ただし、分譲地の場合は事情が少し異なるようです。
土地の引き渡し前の段階では、ローンを実行することが法律上できないためです。
私の場合は、売買契約の締結は2025年7月ですが、住宅ローンの実行は2026年1月に設定されました。これにより、約6か月間の余裕をもって住宅プランを検討できることになり、少し安心しています。
そして、実際の土地引き渡しは2026年2月となる予定です。
文字だけだと分かりにくいので通常の流れと今回の流れをカレンダーで示してみました😀


土地引き渡し後の成功と失敗について
参考までに、土地の引き渡し後に予定されているスケジュールは以下の通りです:
- 設計期間:3〜5か月
- 準備期間:1.5〜2か月
- 工事期間:4〜6か月
👉 合計で約8.5〜13か月かかる見込みです。
つまり、設計開始から着工までだけでも約4.5〜7か月かかるということがわかります。
一方で、先ほどのカレンダーを確認すると通常の流れでは土地契約から引き渡しまでの期間が約2か月と短いため、この間に設計を終わらせるのは現実的にはかなり難しいと感じました。
結果として、土地引き渡しからしばらくして着工というスケジュールになり、
その間に借りているつなぎ融資の利息が発生し続けることになります。
この利息は場合によっては数十万円単位で負担増になる可能性もあります。
ただ、今回の我が家のケースでは、契約から引き渡しまでが7か月と長めだったため、
この間にじっくりと設計を進めることができそうです。
その結果、土地引き渡しのタイミングと同時に着工できる見込みとなり、
つなぎ融資の借入期間も短く抑えられそうです。
これによって、利息負担を最小限にできるのではないかと期待しています😄
土地購入にかかる諸費用まとめ|シミュレーションあり
土地の取得にかかる諸費用の一覧表を不動産会社からいただきました。
ここでは、私のケースをもとに内容を整理しておきます。
● 所有権移転登記費用(司法書士報酬含む)
- 金額:21万円
- 内訳:登録免許税+司法書士手数料
- 司法書士は不動産会社の指定で、自分では選べませんでした。
実は私は登記について少し勉強しており、自分で手続きしたいと思っていたので、選択肢がなかったのは残念でした😁
とはいえ、大切な書類を預けるため、不動産会社が司法書士を指定するのは一般的なようです。
銀行はたいていの場合、指定の司法書士がいるのでさらに自由に選べるケースはないでしょう。
ネットでは、不動産会社によっては不当に高額な設定をしている場合もあるという情報も見かけたため、相場観を持っておくことは大切だと感じました。
● 登録免許税の相場計算
登録免許税を正確に把握するため、以下のような価格体系と係数を参考にしました。
- 固定資産税評価額:実勢価格の約70%
- 路線価:実勢価格の約80%
- 公示価格:実勢価格の100%
- 実勢価格:110〜120%(調整係数)
土地の所有権移転登記にかかる軽減税率は1.5%です。
そこで、登録免許税の見積もりとして以下のような計算を試みました。
実勢価格は購入申し込みをした土地そのものの価格になります。
実勢価格1820万円 × 0.7(固定資産評価額の係数) ÷ 1.1(調整係数) × 1.5% = 約17.3万円これにより、司法書士の報酬は 21万円 − 17.3万円 = 約3.7万円と推定されます。
ただ、一般的に司法書士の報酬は
- 売主強気の価格 15万円
- 銀行指定 13〜14万円
- 安い場合 10万円
と言われているため、この計算にはややズレがあります。
そこで、別のアプローチとして、路線価をもとに固定資産税評価額を使って計算してみました。
60200円/㎡(路線価) × 182.8㎡ × 0.7(係数) ÷ 0.8(調整係数) ≒ 11万円(登録免許税)路線価について簡単に説明します。


出典:全国地価マップ
この場合、司法書士の報酬は 21万円 − 11万円 = 約10万円となり、報酬額に関しては妥当(むしろ良心的😀)な価格設定であったことがわかりました。
● 抵当権設定費用(つなぎ融資を使う場合)
私たちの場合つなぎ融資を利用する際は17万円ほどの用意が別途必要になってきます。
つなぎ融資…金利も高いのに登録免許税も高い。
恐ろしいローンです😱
- 登録免許税:借入額 × 0.4%
- 司法書士報酬:3〜5万円(相場)
- 目安:借入額3000万円 × 0.4% + 5万円 ≒ 約17万円
抵当権設定登記は通常、銀行指定の司法書士が行います。
このような登記は個人で行わせてくれないことが多いそうです。
● 固定資産税・都市計画税
土地の引き渡し時に、月割で精算されます。
これは一般的な費用です。
まだまだ先の支払いになりそうです。
● 仲介手数料
今回は分譲地の購入だったため、仲介手数料は発生しませんでした。
ただし、これは「無料でラッキー」とは一概に言えず、土地代金に含まれていると感じています。分譲地は周辺のそうでない土地と比べて割高なので😓
まとめ|2年間に及ぶ土地探しを終えて…今のところは成功


土地の申し込みから引き渡し、登記やローン手続きに至るまでの一連の流れは、初めて経験する人にとっては不安や疑問の連続だと思います。私自身もひとつひとつ確認しながら進めてきました。
今回の記事では、そうした自分の経験をもとに、手続きや費用の内訳、注意点などを具体的にまとめてみました。
約5年間、嫁さんは土地情報をチェックしてくれていました😲
家を購入しようと決めた直近の2年間は毎日チェックしてくれていまいた。
そのおかげで、今回の土地が出た瞬間にすぐ購入の判断をすることができました。
本当にありがとう、嫁さん😘
そんな嫁さんは土地探しという日課が終わった今は、理想の間取りを探す旅に出ています😄
とはいえ、時々まだ土地情報を見ては——
「えっ、隣の分譲地が大手ハウスメーカーに買い占められてる!
坪単価、うちより3万円も安いんだけど!!」
と、興奮気味に話してくることもあります(笑)
そんなときは、
「土地代を安く見せて、オプションで差額を回収するのが大手HMの典型的なやり方だよ」
といった会話をしています。
今回の記事の内容はあくまで一施主のケースですが、少しでも読み手の方が「次に何をすればいいか」が見えるようになっていれば嬉しいです😄
そして――
ここまでじっくり読んでくださったあなたは、本当に勉強熱心な方だと思います😀
情報を集めて考える力こそが、後悔しない家づくりにつながると私は感じています。
これからも一つずつ、一緒に前に進んでいきましょう。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
ブックマーク宜しくお願いします✨