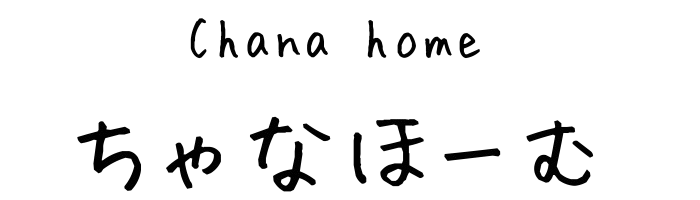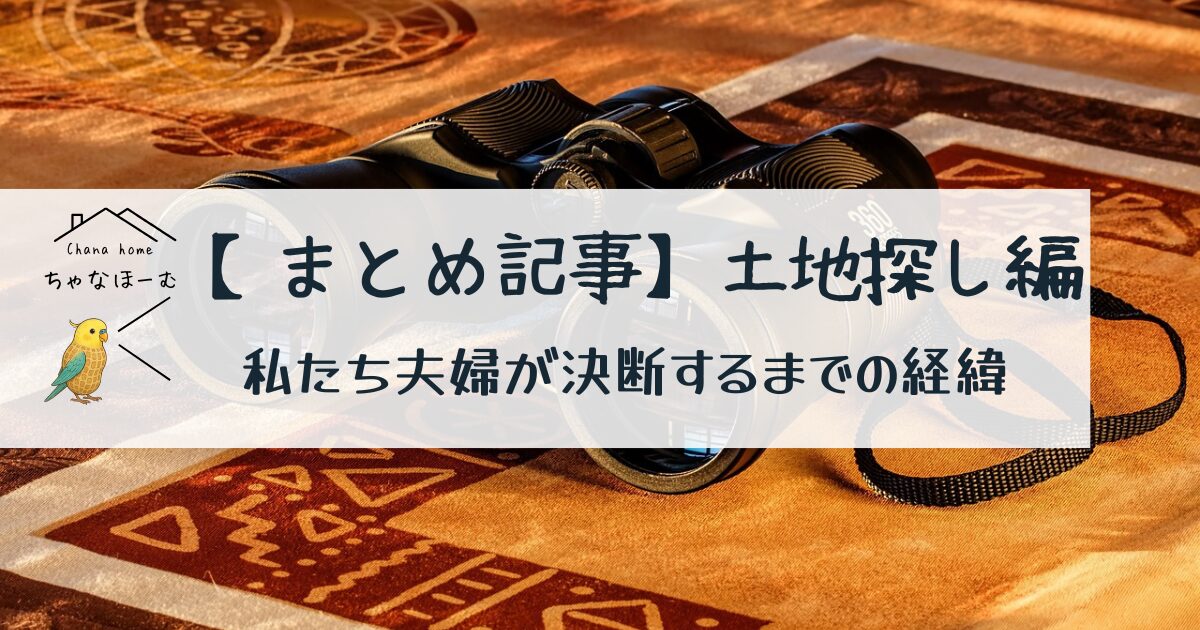「ネットで土地探してるけど、いい物件っていつもすぐ売れてて…やっぱりタイミングの問題かなあ?

実は、ネットに出た時点でもう“売れ残り”の可能性が高いんだよ。私も5年かかったけど、鮮度の高い情報の取り方にコツがあったんだ
「土地探しがこんなに大変だとは思わなかった…」
そんなふうに感じていませんか?
私たち夫婦も、5年間にわたり土地を探し続け、ようやく納得できる分譲地にたどり着きました😀
この記事では、
・なぜ土地探しが長引いたのか
・どこで情報を得たのか
・購入の決め手は何だったのか
・もっと効率的な探し方はあったのか
といった点を、私たちの体験をもとに詳しく振り返ってみます。
ネット検索だけでは出会えなかった「鮮度の高い土地情報」を得るために、どんな工夫をしてきたのかも紹介します。
土地探しに悩んでいる方が、次の一歩を踏み出すヒントになればうれしいです。

この記事を読むと分かること
- 家づくり構想8年・土地探し5年と長期戦になった理由と再度検討を始めた理由
- 不動産会社とのやり取りを通じて、ネットに出る前の“鮮度の高い土地情報”を得る方法
- 土地購入の判断材料となった「相場観の養い方」や「土地条件リスト」の活用方法
- 人気分譲地を見逃さないために実践した、不動産会社との効果的な関係づくりと問い合わせの工夫
土地探し、疲れた?|なぜ土地探しが長引いたのか?
今から8年前、私たちは家づくりを本格的に始めようと、まずは半年ほどかけて情報を集めたり勉強をしたりしていました。
その流れで土地探しも始めようとしていたのですが、思わぬ事情でストップがかかりました。
勤務先の会社が移転するという話が持ち上がったのです😫
私の所属する部署は建物ごと現状維持となったものの、会社全体の多くの機能は新たな場所へ移ることに。
「今ここに家を建てても、数年後に自分たちも異動になったらどうしよう」
そんな不安が拭えず、家づくりの計画はいったん中断することになりました😥
会社の経営者の立場で考えれば、部署が中途半端に残るメリットは少ないだろうと感じました。
このまま進めるのはリスクがあると思ったのです🤔
土地探し、疲れた?|再び家づくりへ前進するきっかけ

状況が変わったのは、コロナ禍以降です。
リモートワークが当たり前になり、場所に縛られずに仕事ができるという実績が社内でも積み重なりました。
この環境であれば、会社があえて費用をかけてまで私たちの部署を移転させる可能性は低いだろう、という予測(かなり希望的)ができるようになりました。
さらに、社長から「会社の移転は今後も予定していない」と明言されたことも後押しになりました。
ただ、正直に言えば会社側の言葉を完全に信じることはできません。これまでの経験上、方針が変わることは珍しくないと思っているからです😅
土地探し、疲れた?|それでも家づくりを再開した理由

5年前、会社の社宅の居住期限が切れました。
そのタイミングで私たちは築45年の戸建てを借りて住むことになりました。
老朽化が進んでおり、断熱や設備面でも不便なことが多い家でしたが、家賃が抑えられることもあり、今もその場所で暮らし続けています。
ネズミの足音が天井裏から聞こえてくる、どこから入ってきたかわからないコウモリが部屋の中を飛んでいる(2回ほどありました)😅
そんな家ですが広いし、庭もあり私はそこそこ気に入っていました😁
私はしばらく家を建てるという考えから離れていました。
けれど、妻は違いました。土地や中古住宅の情報を地道に探し続けていたのです。
私はこのまま賃貸でもよいし、戸建てなら中古物件でも良いと思い何軒か中古物件も見ましたが
「私は新築に住むために働いている!」
と嫁さんからチャンチャン言われ、ライフプランを作り、予算を決めて新築の検討を始めました。
今から、2年半前くらい前の出来事になります。
そして、今年の2月に家づくりの勉強がひと段落。5月には工務店が絞れてきたのでそこから本格的に不動産屋をめぐる土地探しを再開しました。
ですので、本格的な土地探しからわずか2か月ほどで申し込みを出したことになります。
嫁さんの土地の相場観と土地探しチェックシートのおかげで早い決断が出来たと思います。
我が設計士さんにもすでに私たちが建てたい建物規模、要望に関する情報を出していたのでアドバイスをもらいつつ設計者目線での土地選びをする事が出来ました。
土地探し、疲れた?|決断と経緯 ~おすすめサイトと相場観の育て方~


ここからは具体的な探し方についてです。
我が家の分担として土地探しは嫁さん、家本体は私とおおよそ担当がわかれています。
そんな訳で嫁さんに探し方を聞いてみました😀
情報収集に使ったサイトと私たちの探し方
土地探しを始めると、まず目につくのが不動産ポータルサイト。
ネットでよく見かける意見としては、
- 「アットホームにはほとんどの土地情報が載っている」
不動産のことなら【アットホーム】物件探しから住宅情報まで! - 「ハウスドゥには、それ以外の独自情報がある」
【ハウスドゥ.com】不動産・住宅の購入や売却に関する情報が満載!
といったものがありました。
新着通知機能を活用し、最新の情報を逃さないようにするのが基本の探し方のようです。
もう一歩踏み込んで調べてみると、
- 「ニフティ不動産は8つのサイトを横断検索できる」
不動産・住宅情報をまとめて検索【ニフティ不動産】 - 「アットホームはニフティ不動産と提携、ハウスドゥは提携していない」
という情報も出てきました。
つまり、「ニフティ不動産+ハウスドゥ」を組み合わせることで、幅広く情報をカバーできるのではないかと考えました。
そんな話を私は得意げに妻に語りましたが、実際に妻がよく見ていたのはアパマンショップでした。
理由を聞くと、「なんとなく」とのこと。
【アパマンショップ】賃貸マンション・アパートの賃貸住宅情報・お部屋探し
結局ネットでは後述する通りあまり良い情報が回ってこないのでこだわらずに相場観を養う程度で良いと思います。
相場観はどうやって身につけた?
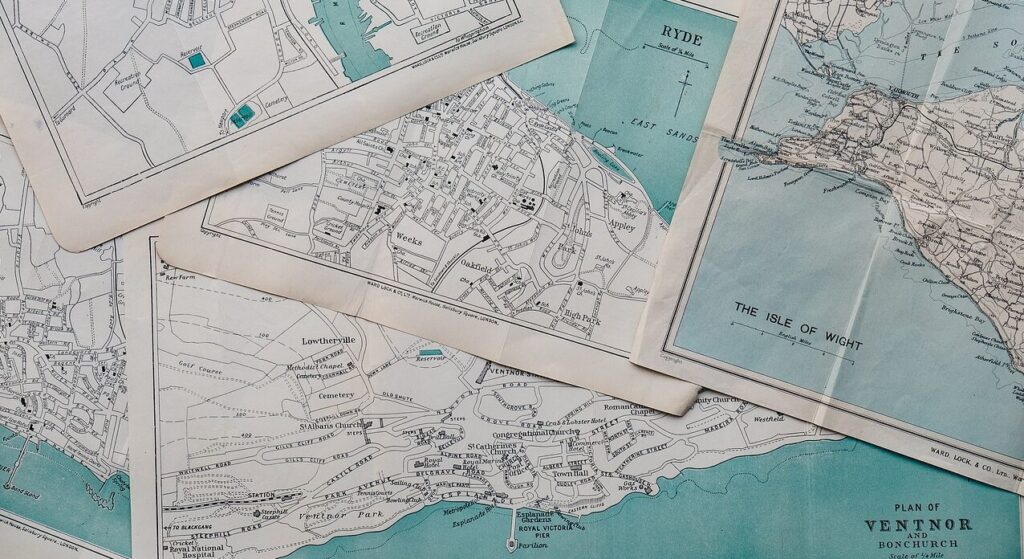
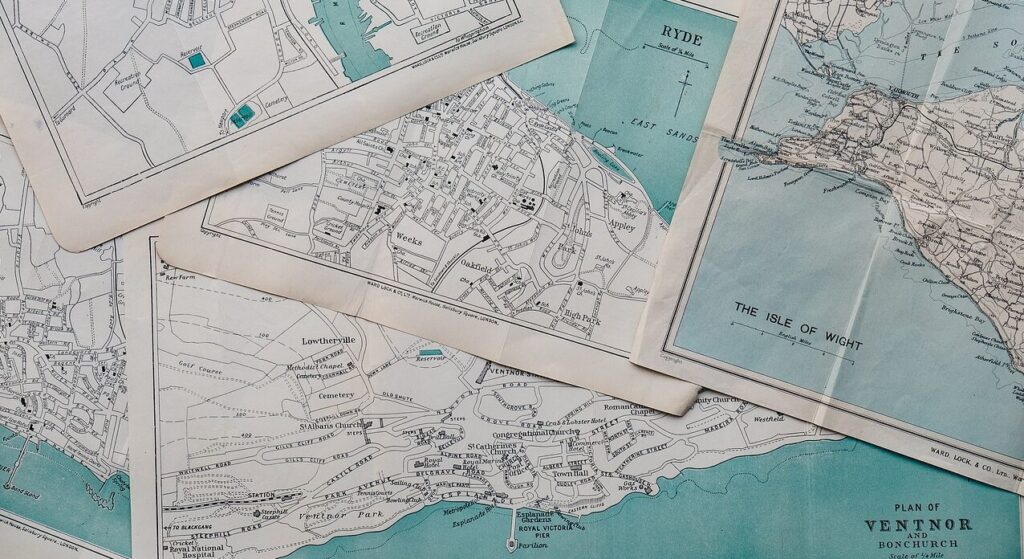
妻は、地図を確認しながら出てきた土地の条件と価格差に注目して相場観を育てていたようです。
- 「距離的には近いのに、なぜここだけ価格が高いの?」
- 「市が違うだけで、どうしてこんなに金額が違うんだろう?」
- 「背後に山があるのに高値設定…これは強気の価格だな」
そんな疑問を持ちながら物件を見ていくと、自然と相場の感覚が身についていったそうです。
私「相場観ってどの位で養えるの?」
嫁「土地情報は1回見れば覚えているから時間はかからないよ」
1回見れば覚えられる。。。かっこいい。頼りになる😍
また、ネットで過去の販売情報やチラシを探してみると、当時の坪単価と再販時の価格の差なども確認できる様です。
「え?最初に売られていた時よりも、再販売の方が高くなってる…?」
そんな情報を見つけては楽しそうにしていました。
この「土地の相場観」は、後に購入を決断する際、大きな支えになってくれました。
土地探し、疲れた?|決断と経緯 ~購入の決め手は?~
私たちが土地選びにおいて優先した項目は以下の3つです。
- 価格
- 大型分譲地であること
- 周辺に生活施設が揃っていること
上から順番に優先度が高いです。
ハザードマップに関しては、希望する土地が該当区域に入っていた場合は購入対象外とする方針だったため、優先順位には入れていません。(※詳細は別記事をご参照ください)
まず何より、価格が折り合わなければ手が出せないため、価格を第1優先にしていました😅
という事で、実質的に私たちがもっとも重視していたのは「大型分譲地であること」です😄
なぜそこまで大型分譲地にこだわったのかについても、別記事でご紹介しています。
NG条件をあらかじめ明確にする
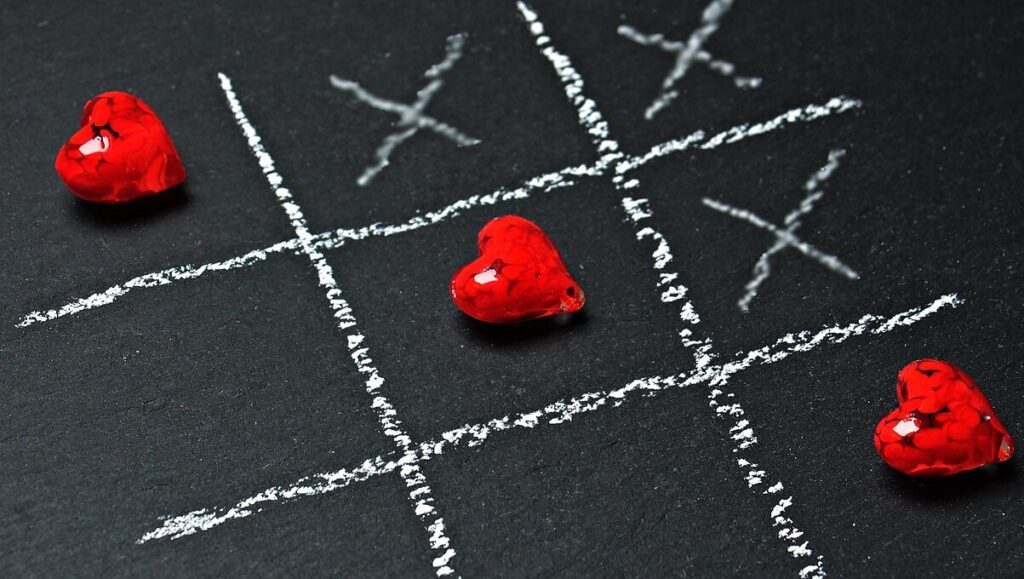
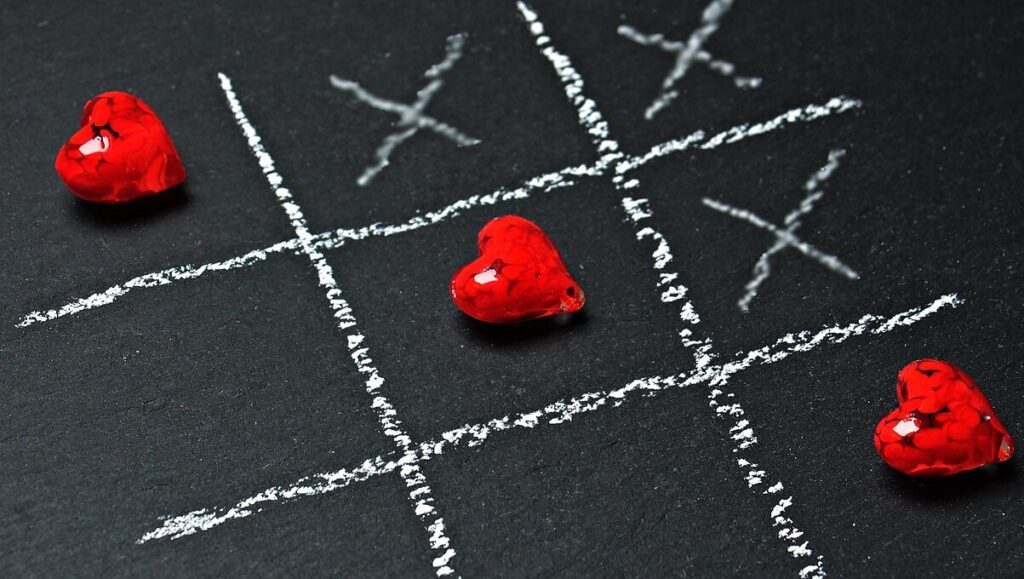
また、ハザード関連以外で「これは避けたい」という条件を最初から明確にしておくと、土地の候補をスムーズに絞り込むことができました。
私たちの場合、以下の3つがNG条件でした。
- 検査済証の交付を受けていない擁壁がある土地
- 私道が共有ではなく分割になっている土地
(道路掘削、維持管理の覚書、通行承諾などが整っていれば分割でもOKとしました) - 土壌汚染や埋設物について、重要事項説明書で「免責」とされている物件
いずれも、後から大きな金銭的負担が発生し、家づくりそのものが立ち行かなくなるリスクがあるため、避けるようにしていました😅
過去の分譲地から信頼性を見極める
分譲地開発をしている不動産会社の造成状況を確認するため、過去に販売された分譲地をGoogleマップでチェックしました。
- どんな家が建っているか?
- 区画や道路の整備状況はどうか?
そういった点を見て、「この会社の分譲地なら安心できそうだ」と判断材料にしていました。
嫁は、Googleマップでのお散歩がすっかり趣味のようになっていました😁
土地は、実際に歩いてみてから
相場観や過去の事例による「判断軸」ができてくると、土地選びのスピードも早くなります。
ただし、どれだけ条件が良さそうに見えても、実際に現地を歩いてみることは欠かせません。
不動産屋さんの説明では、周囲の雰囲気や土地の微妙な高低差、音の反響など、細かな情報は伝わりません。
先述した、購入希望エリアの相場観と過去物件のチェックで購入判断の軸を作った上で先の記事にあるチェックシートを活用しながら紹介された土地は実際に入念に歩いてみてください
不動産屋にいくら良いと勧められても話だけではその土地の悪いところは伝わってこないのです😣
運命の土地との出会い
ある日、何度か訪れていた不動産会社の店内で、ふと壁に貼られていた計画図が目に留まりました。
「この土地は、いつから販売されるんですか?」
と聞いたところ、
「まだ日程は未定ですが、1か月以内にDMをお送りします」
という返答。
この土地が、後の私たちにとっての「運命の土地」となりました。
ちなみにこの分譲地、販売方法は「先着順」ではなく「くじ引き方式」で優先順位を決めるというものでした。
希望していた第1希望の区画は残念ながら外れてしまいましたが、最終的に申し込みを出した「南東・北の角地」は、私たちにとって納得のいく良い選択だったと思っています。
土地探し、疲れた?|決断と経緯||もっと効率的な探し方はあったのか?
土地探しを5年間続けてみて思うのは、ネットに出てくる情報だけでは限界があるということです。
個人的におすすめしたいのは、不動産会社に一度足を運び、その後も定期的に連絡を取るという方法です(スミマセン正攻法です😁)
というのも、新しい分譲情報が出たとき、不動産会社はまず「その土地を希望している人」に連絡を取ります。
この時点で人気のある区画は、どんどん申し込みが入っていきます。
そして、結果的に残った区画がネット上に掲載される、という流れが多いようです。
そして新規の大型分譲地は人気がありすぎて区画が残ることがほとんどありません。
もちろん全ての不動産会社がそうとは限りませんが、私たちが接した会社では、だいたい似たようなパターンでした。
つまり、ネットに出ている土地情報は、すでに一次選考を経た“残り”であることも多いということになります。
土地がネットに出るまでの流れから申し込み1番手のヒントを得る


実際の流れとしては、おおむね次のようになっているそうです。
- 分譲地を計画する
- 過去に希望条件を伝えていた顧客にDMを送る
- DMを受け取った顧客が購入申込書を提出する
- 申込が入らなかった区画がネット上に掲載される
ここで注目すべきは、2と3の間の“数日間”です。
このタイミングで“たまたま”不動産会社を訪れていた場合、先着で申し込みができる可能性があります。
“たまたま”を引き寄せる方法


こういった確率を少しでも高めるために、私が実践していた方法があります。
それは、一度不動産会社を訪れて、希望条件リストを渡し、月に一度程度のペースで問い合わせを続けるということです。
たとえば、こんなやり取りをしていました:
私:「御社では、土地情報の更新は何曜日が多いですか?」
不動産屋:「○曜日ですね」
私:「その曜日でどの日に行けば良い土地情報に出会える可能性が高いですか?」
不動産屋:「(※内心“〇日にあの土地の情報が出てきそうだな…”)○日なんて、いかがでしょう?」
このように、後で教えてもらいましたが不動産屋さんはこんな事を考えていたようです。人によるとは思いますが少しでも申し込み一番手の可能性は上がるのではないでしょうか?
もちろん、担当者の考え方や会社のルールにもよると思いますが、確率を少しでも上げる努力はしておいて損はないと思います。
私の場合、何度かこの方法で「DM発送直後の土地情報」を紹介してもらうことができました。
ただし、「DMを発送する前の土地情報は紹介できない」というルールもありますので先ほどの2,3の間を狙いたいですね😀
土地探しを効率的に進めるには、ネットだけに頼らず、不動産会社との信頼関係を築くことが鍵だと実感しています。
条件リストを渡し、適度なタイミングで丁寧に連絡をとることで、運命の土地と少し早く出会えるかもしれません。
土地探し、疲れた?|決断と経緯 ~探し方いろいろ~


これまでの経験を通じて感じたのは、最終的には「不動産会社との直接的なやり取り」が、最も鮮度の高い土地情報につながるということです。
ここでは、その方法以外に私たちが試した/検討した土地探しの手段をまとめてみます。
人によって合う合わないがあると思いますので、あくまで参考程度に読んでいただければと思います。
① 工務店やハウスメーカーにお願いする
住宅会社の中には、不動産情報を扱える部署を持っているところもあります。
また、工務店やハウスメーカーは「レインズ(不動産業者向けの物件流通システム)」を閲覧できるため、土地探しを依頼することは可能です。
ただし、あまり過度な期待はしない方がよいかもしれません。
依頼する際は、以下のように「本気度」を伝えることがポイントです。
- 御社で建てたいと思っている
- すぐにでも建てるつもりである
- ローン審査も通っている
こういった姿勢を見せることで、営業さんも真剣に動いてくれる可能性が高まります。
この方法のメリットは、土地と建物の予算バランスを住宅会社が把握してくれる点です。
土地に予算をかけすぎて、建物に手が回らなくなるような事態は避けやすくなります。
ただし、不動産部門を持たない住宅会社では、土地情報の鮮度や量が我々と大差ないことが多いです。
特に新規分譲地については、開発業者の不動産屋は住宅会社よりも「希望を出している顧客」へ先に情報が届くことが多いようで、工務店やハウスメーカーには情報を出してくれないようです。
このあたりは会社ごとの方針にもよるので、事前に確認しておくと安心です。
② 散歩で見つける


地域によっては、インターネットを使わない不動産会社もあり、そういった物件は「看板」が唯一の情報源ということもあります。
実際に地域を歩いて探す、という方法も一定の効果があります。
ただ、私たちが狙っていたのは大型分譲地だったため、この方法はあまり適しませんでした。
分譲地は、造成が始まるより前に話が進む為、造成地を見つけた頃にはすでに申し込みが終わっていることも多いからです。
私たちのような条件が無い場合や、ピンポイントで探したいエリアがある場合には、試してみてもよいかもしれません。
また、「売地」でなくても登記簿(謄本)を取り寄せて、信頼できる不動産会社を通して交渉する、という上級テクニックを使っている方もいました。
③ 賃貸専門の不動産に聞いてみる


賃貸物件を扱っている不動産会社にも、地元の地主さんとつながりのある方がいます。
「このあたりで将来的に土地を出すような話があったら、ぜひ教えてください」と伝えることで、思わぬ情報が入ることもあるようです。
今住んでいる賃貸の不動産屋にまずは声をかけてみてはどうでしょうか?
ただ、私たちのように分譲地を探しているケースでは性質が合わないと感じ、積極的には使いませんでした。
④ 銀行で土地を探す


銀行の資産活用窓口というルートもあると聞き、検討はしてみました。
支店長代理クラスの方が対応してくれることもあり、地主とのつながりを活かした紹介が期待できるそうです。
行くタイミングとしては、午前中の比較的落ち着いている時間帯が良いとのこと。
「地主とつながりがあると伺っています。土地を出す予定の方をご存知でしたらご紹介いただけませんか?」
と丁寧に相談することで、対応してくれるケースもあるようです。
その場合は、当日中にお礼の連絡をするのがマナーです。
⑤ 市区町村の保有地売払い情報
地方自治体が保有している土地を、一般に売り出すケースもあります。
これは定期的にホームページで公表されていることが多く、不動産仲介手数料が不要だったり、相場より安く購入できる可能性もあります。
ただし、物件の数は限られており、住宅用として使える小さい面積の土地が出てくるかはタイミング次第です。
自分で定期的に確認する必要があるのが少し手間ではあります。
⑥ 区画整理地や競売物件


市区町村による区画整理事業や、裁判所による競売物件も選択肢としてはあります。
ただ、瑕疵担保責任(欠陥などの責任保証)がない、権利関係が複雑といったリスクもあるため、私たちは情報を見る程度にとどめました。
土地探し 疲れた?|決断と経緯 まとめ
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
細かい情報が多かったかもしれませんが、最後まで読んでくださったあなたは、かなりの勉強家だと思います。
その真剣さが、きっと理想の土地との出会いにつながっていくはずです。
今回の記事をまとめると――
もっとも鮮度の高い土地情報を得るには、不動産会社に希望条件を伝えた上で、定期的に連絡を取るという王道にプラスしてちょっとした工夫で少しでも申し込み順序を上げるという話をしました。
もちろん、工務店への依頼や地域を歩く、自治体の情報を確認するなど、他の方法にも一定の可能性があります。
けれど、最終的には「人と人との信頼関係」が、土地探しの精度とスピードを大きく左右するというのが私たちの実感です。
そして、土地が見つかった後も、やることは山積みです。
購入申込書を提出してから契約までの約1週間で、その土地に希望の家が無理なく収まるかを見極める必要があります。
そのためには、事前のシミュレーションと設計士を巻き込んだ準備がとても重要です。
(わずか1週間で希望の間取りがその土地に入るかを判断するなんて…用意無しでは無理です)
▶︎【対策記事はこちら】
土地探しは、情報収集と人とのつながり、そして自分たちの判断軸をどう持つかが鍵になります。
あなたの土地探しが、よりスムーズで納得感あるものになるよう、少しでもお手伝いできれば嬉しいです。