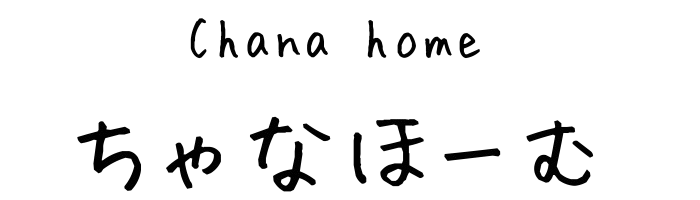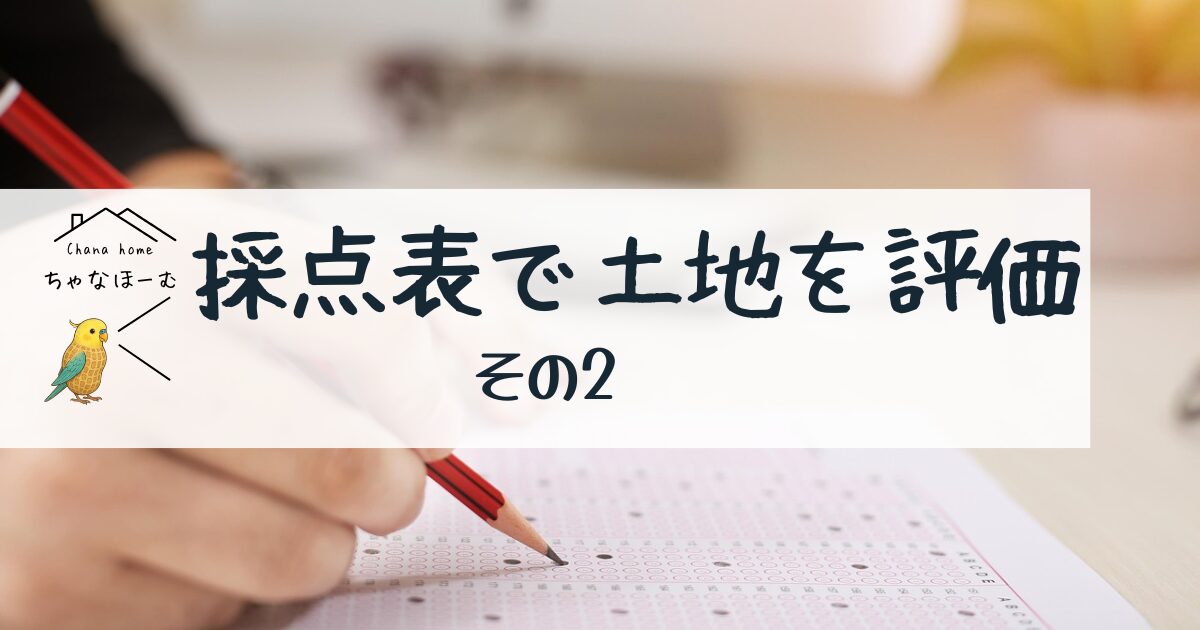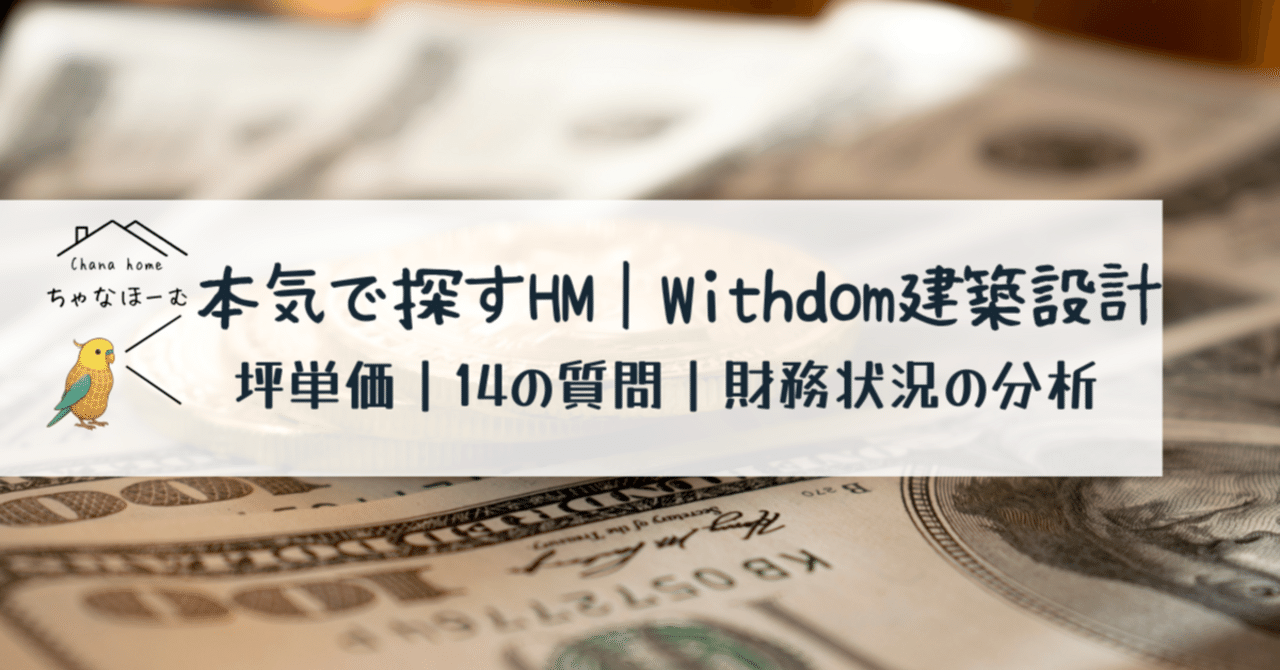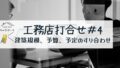今までの総まとめ。
断熱等級7(33坪)で価格比較しました 。・ヤマト住建
・地元工務店
・一条工務店
・ウィズダム建築設計
・大和ハウス
・三井ホーム
・アキュラホーム
・クレバリーホーム
・住友不動産1千万円以上の開きになるとは思いませんでした…勉強不足。
計110時間のやり取りを集約 家造り時間の節約になると思います。※有料Note

この採点表、めっちゃ細かくない?こんなにチェックしなきゃダメ?

逆に言うと、これだけ見ておけば後悔のない土地選びが出来ると思うよ!
前回ご紹介した土地採点表、ダウンロードしてみたものの「この項目って何を見ればいいの?」「なんでここをチェックする必要があるの?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
たしかに、土地選びには地盤やインフラ、法律的な制限、周辺環境など、見慣れない項目が多く、表だけでは判断に迷うことも少なくありません。
私自身、土地選びに2年かけて調べ上げ、試行錯誤しながら作ったチェックリストです。
本記事では、採点表の各項目について解説しながら、「なぜこのポイントを見逃してはいけないのか」をひとつひとつご紹介します。
この記事を読み終える頃には、「この土地、価格は安いけどここがネックだな」と冷静に判断できるようになり、土地探しの軸がブレなくなります。
土地選びの不安を、納得と確信に変えるための実践的なガイドとして、ぜひ活用してください。
とはいえこの記事は長いです😅
チェックシートを読んでみて疑問に思った項目だけ確認していきましょう!
敷地条件

チェックシートの予算、エリアに関しては特に説明は不要だと思いますので敷地条件の解説からスタートしますね。
分譲地(8~10区画以上の新しいコミュニティがある)
新規の大型分譲地では、同じタイミングで家を建てる世帯が集まりやすく、自然とご近所付き合いが始まります。似た価値観の人が集まりやすく、治安も良好に保たれやすい傾向があります。生活環境の安心感を求めるなら、分譲地の規模にも注目です。
インフラや道路が新しいので相場より割高で狭い土地が多いが長い目で見れば割安という特徴もあります。
私個人としての分譲地への優先度は高いです。
この記事にもあるように古い土地に絶対に行きたくない!
仕事でもペコペコしているのにプライベートでもペコペコしたくない。。。
早く家建てたい😥
広さ

・仮間取りがはいるか?(駐車場や庭スペースも要確認)
理想の間取りを実現するには、土地の広さだけでなく形状も重要。特に地形が歪だと、広くても間取りに制約が出ます。庭や駐車スペースを確保しつつ仮の間取りが入るかを見てもらうのが最も確実な確認方法です。
その為にもこの記事で進めている通り土地を探す前に仮の間取りを決めておくことをおすすめします。
・間口(最低でも9m、間口四間の家が基準)
間口については4間(約7.3m)の家が最低限(これ以下はプランの幅が狭くなる)欲しいことを考えると間口は9mは欲しいです。間口が広くても仮に前面が南道路の場合、幅が5mなど狭いと日当たり望めない可能性があります。道路幅が狭くても敷地に7m+道路5mだと日当たりが良いですが敷地内に7mもスペースをとるのは現実的ではないです。
例えばサッシの半分くらい日が入ればよい。など設計士のコメントをもらいつつ日当たりの程度を理解したうえで購入検討を進めましょう。
日当たりは後悔ポイントNo1になりがちです。
2Fリビングなど設計で工夫できるとこともありますのでその設計のデメリットを覚悟したうえで土地を優先するという判断も良いと思います。
個人的には毎日疲れ切って帰ってきて2Fに上がっていくのはしんどいので1Fリビングが良いです😁
・奥行(短すぎず長すぎず、バランスが重要)
奥行が極端に長い土地は、家の配置が一方向に偏りがちで、庭や駐車場の動線にも影響が出ます。あと奥に行くほど日当たりが悪くなるのもマイナスですかね。
私の狙う分譲地は間口が狭く奥行きがある物件だらけです。
もう少し間口の広い土地を開発してほしいです。。。😥
逆に短すぎると、2台駐車+玄関アプローチが窮屈になり、掃き出しサッシと車の距離が短くなり圧迫感が出てしまうといった後悔も聞いたことがあります。
ただ間口の方が間取りに対しては支配的ですので奥行はよほど短くない限り間取りでカバーできると思います。設計士に頑張ってもらいたいところです(他力本願😋)
・地形(整形地がベスト、変形地は要注意)
整った長方形の「整形地」は設計がしやすく、土地の価値も安定しています。一方で旗竿地や台形地などの変形地は価格は割安でも、プランニングに制限が多くなり建物自体のコストが高くなりがち。見た目以上に使い勝手に影響するので慎重に判断を。
・庭の広さ(家~フェンスまでの距離)
庭スペースは、仮間取りを用いて広さをシミュレーションしてみます。庭としてどれくらいのスペースが必要なのか?をメジャーを使って外でイメージしてみましょう。家~フェンスまでの距離を自分の体を使ってイメージする事が良いと思います。
日当たりに関して言うと、南側を庭にする場合、冬至に1階で日差しを確保するには隣家と11.4m以上、2階でよい場合は5.7m以上離す必要があります。南側の前面道路が6mの場合、冬至に1階で日差しを確保するには庭(家~フェンス間)を5.4mとれば良いという計算になります。
そんなに広く庭が取れないという場合、隣家が総二階の切妻の場合、隣家との距離が8mあれば冬至で日がサッシ面積の3/4に日が入ってきます。ちなみに6mでわずかしか日が入らず、4mで入らなくなるので注意しましょう。
先述した通り、日当たりの悪さは後悔ランキング1位です😱
角地

・方角(隣接道路の幅と方角に注意)
隣接する道路がどちらか狭いと斜線制限にかかる、道幅が狭いと向かいの家の影に入るなどのデメリットがあります。これらを解消するためには道幅6mはほしいところです。
第一種低層地域では建ぺい率40%とかなりきつい条件になることがありますが。角地は10%緩和されるなどがあります。ただし容積率の緩和はないので注意が必要です。
また角地はごみ置き場に指定されがち、電柱や道路標識が設置されることもあります。可能性を不動産屋に確認してください。
・隅切り(敷地が削られていても“接道”とは限らない)
角地で「隅切り」があると、実質的な建築スペースが狭くなることがあります。前面道路が6m以下だと必要です。大きさは市町村で違うので注意しましょう。購入予定地の分譲地の土地の形状でおおよその隅切り量が予測できると思います。
日当たり
・道路の向き(南道路×南片流れ屋根=要注意)
東道路と西道路に面した土地では、南側に太陽光付きの片流れ屋根がある家が建つと、冬の日当たりが大きく遮られます。屋根形状や向きによっては、自宅の室内が年中薄暗くなる可能性も。道路と隣家の配置関係に注意を。
特に一条工務店の様に30度の屋根角度で片流れのパターンが最悪なのでその土地にどのハウスメーカーが家を建てそうなのか不動産屋に確認してみましょう。
実際私の家の南西にアパートがあり午後14:30以降の日当たりが絶望的、冬めちゃくちゃ寒いです😥
南側だけでなく南西、南東の建物の高さにも注意を払ってください。
・東西の状況(隣家の奥行きのズレに注意)
隣家が前後にズレて建っていると、↑と同様に自宅の窓に影を落としやすくなります。特に朝・夕の採光に直結します。隣地の建物ラインが自宅のどの窓に影を落とすか、現地で光の入り方を確認しましょう。
ただ、いっせーのせっ!で家が建つ分譲地では隣家の状態がわからないので注意が必要です。
建築確認申請が出ているであろうタイミングで役所に問い合わせると配置計画がわかりますので確認してみるのも手かもしれません。
・道向かいの南東・南西の状況
道向かいの家が2階建てで高さがあり、南東・南西方向に位置していると、先述した事と同様に朝晩の光を遮ることがあります。敷地の南側が開けていても、斜め方向の建物次第で日照時間がガクッと減るので要注意です。
・南の状況(抜け感と遮蔽物に注目)
日当たり重視なら、南側の抜け感は必ずチェック。高い建物や植栽があると、思ったより光が入らないことも。建築予定の家が何階建てか、将来的に建て替えの可能性はあるかなど、現状だけでなく今後も含めて考えましょう。検討する時は最悪状態を視野に入れて日当たり検討をしてみましょう。
・南隣家との距離(近すぎると暗くなる)
南側の隣家が近すぎると、特に冬場の日照が確保できなくなります。「庭の広さ」の項目で書いた通り意外と南にある家との距離は必要です。
隣地との境界

境界問題は非常に厄介で複雑です。
分譲地にはない問題だとおもいますがぽっと出の土地を購入する時はしっかり情報を集めてください。
不動産屋に聞けば情報は出てきますが「聞かないと答えてくれません」
相手は敵ではありませんが味方でもないという事を意識しておきましょう。
契約時の重要事項説明書の備考に記載はありますが何時間も説明があった後での備考説明です。
疲れてる時に重要なことを言われても頭に入ってこないです😪
・確定測量図+隣地所有者の認証印 or 地積測量図
土地の境界が曖昧だと、建物配置や外構に支障をきたす可能性があります。確定測量図や隣地所有者の認証印は、将来的なトラブル防止のためにも取得必須です。測量図がxyz座標で記されていれば精度も安心です。
よくわからない用語の連発で失礼しました😅
この境界問題に関しては後悔ポイントとなる人が多いのでここで詳しく見ていきましょう👍
境界確定測定(隣地との正確な境界線を確認)
土地購入後のトラブルで多いのが「境界問題」。特に境界杭や測量図が曖昧だと、後から隣人と揉めたり、建築許可に支障が出ることも。購入前に「境界確認書」や「確定測量図」を用意するには、隣地の所有者の立ち会いや印鑑が必要で、費用も数十万〜100万円かかる場合があります。Googleマップの面積と実測値が大きく異なることもあるため、古いデータしかない場合は次に示す特約で再測量を依頼しましょう。
契約特約(境界の明示を売主に義務づける)
境界に関する曖昧さを残したまま契約すると、先述の通り後から高額な費用が自己負担になるケースも。契約書の特約に「売主負担で境界を明示する」と明記しておけば、購入者が後から交渉する必要もなく安心です。特に私道との境界も含めて、売主側が隣地所有者の立ち会いと認印を得て、専門家が作成した図面を交付する形が理想です。
新規分譲地だと土地の所有者がいないので認印などはなく販売されているのでこういった事を気にしないでいれられるのは気持ちが楽ですね😀
確認順序(契約前にチェックすべき測量図)
境界に関して確認すべき資料には優先順位があります。
① 確定測量図+隣地所有者の認印:これがあればベスト。なければ「引き渡しまでに取得」を条件に。
② 地積測量図:法務局から取得可能。作成時期が古い場合は信頼性に注意。
③ 現況測量図・実績図:売主が持っていることが多いですが、作成者や作成年月日をチェック。土地家屋調査士や測量士の押印がないものは要注意です。
① 確定測量図+隣地所有者の認印(境界トラブルを防ぐ最も信頼性の高い図面)
土地購入における境界の信頼性を担保する最も強力な書類が「確定測量図」です。これは、隣接する土地の所有者すべてと立ち会いを行い、それぞれの認印をもらったうえで作成された境界確定の図面です。境界トラブルを防ぐうえで極めて重要であり、住宅ローン審査や将来的な売却時にも大きな信頼材料となります。
【新規分譲地の場合】
ただし、先述した通り周囲すべてが同一開発業者によって造成された新規分譲地であれば、隣地所有者の認印は不要なケースが一般的です。この場合、業者が一括で測量・境界確定を済ませており、各区画の境界も正確に定められているためです。
一方で、分譲地の一部が既存の宅地や他人所有の土地に接している場合は、その隣地所有者の認印付きの確定測量図があるかを確認すべきです。開発業者が提出する測量図が「外周のみ確定」となっていることもあるため、誤解せず確認しておきましょう。
② 地積測量図(境界の信頼性と復元性を左右する重要書類)
土地の正確な面積や境界を把握するためには、「地積測量図」の確認が不可欠です。特に2005年(平成17年)以降に作成されたものは、XY座標で登録されており、災害や工事で境界杭が動いた際でも高精度で復元が可能です。一方で、1993年以前や三斜法によるものは精度が低く、トラブルの元に。
また、似た名前の「確定測量図」とは異なり、地積測量図は法務局で450円ほどでネット取得できます。特に2010年7月以前のものは測量日時の記載がない場合もあるので、古い図面には注意が必要です。
さらに、「任意座標」や「残地求積」による図面は、実質的に測量図としての価値がない場合もあります。境界確認書や隣接境界証明書と合わせて、精度の高い測量図を確認しておくことが、将来のトラブル回避と資産価値の維持に繋がります。
③ 現況測量図・実績図(あくまで参考図面。登記面積や境界とは別物)
「現況測量図」や「実績図」は、現地の目視や簡易な測量機器を使って、現在の土地の状態を記録した図面です。建築計画の初期段階や、仮の図面として使われることが多く、土地家屋調査士や測量士の押印がないものは登記面積や法的な境界を示すものではありません。
これらの図面には、隣地所有者との立ち会いや同意がないため、境界杭の位置や面積が実際とずれている可能性もあります。あくまで「現状こんな感じです」という目安であり、法的な効力や復元性は低いため注意が必要です。
特に、不動産業者が「現況図あります」と説明してきた場合も、それが確定測量図なのか、現況測量図なのかを必ず明確に確認しましょう。混同して判断すると、将来の境界トラブルや建築の際の支障につながります。
実測売買(登記簿と面積が違う可能性あり)
土地の売買価格を、登記簿の面積で決めるか、実際に測った面積(実測)で決めるかによって、支払い金額が大きく変わることがあります。実測売買を選んだ場合、最終的な面積が登記簿より狭ければ、希望の建物が建てられないリスクも。契約前に「面積差による価格調整」があるかどうかを必ず確認しましょう。知らずに進めると購入後土地代が高くなる、土地が狭くなることがある。建てたい家が建てれないなどのトラブルがあるので実測売買の土地は破談するべきだと思います。
公簿売買(登記簿の面積だけで売買)
公簿売買とは、登記簿に記載された面積でそのまま土地の売買価格を決める方法です。ただし、実際の土地面積と一致しないことも多く、差分による損失が出るケースも。一般的に売主側で確定測量をやります。実測面積を把握したうえで価格交渉をするのが現実的です。誤差があるなら契約書に「誤差の精算方法」や「違約時(期日までに確定測量されなかった時)は白紙撤回」なども明記しておくと安心です。
最近、区画整理された土地などで、公簿面積が信頼できるという場合は、公簿売買でも良いですが実際の数量と一致しないこともありますので注意が必要です。
最近はグーグルマップで囲った土地の面積が測定できるます。
おおよその面積を把握したい場合は活用するのも良いと思います。
・隣家~境界までの距離

隣家との距離が近すぎると、日当たりやプライバシーの確保が難しくなります。また、足場を組む際にも支障が出るため、建築工事自体に制限がかかることも。必ず事前に現地で確認をしておきましょう。
理想的には1m以上
外壁のメンテナンス(塗装・清掃・足場設置)や、将来的な修繕を考慮すると、境界線から1m以上空けるのがベストです。過去に0.9mの位置に透明な引出しサッシがありプライバシーを損害されたという事で慰謝料とルーバーの設置を命じられた判例があります。
施主系ユーチューバーで隣からの苦情で目隠しを設置させられた人もいたので注意が必要です😣
50cm以上1m未満はグレーゾーン
民法上はクリアしていても、実際には施工やメンテナンスに支障が出る場合があります。
50cm未満はリスク高
隣家とのトラブルリスクや、将来売却時に価値が下がる可能性も。
・境界杭の確認
境界杭は土地の明確なラインを示す大切な目印。これが見当たらない場合は、正確な境界が不明でトラブルのもとになります。購入前に図面と現地を比べて境界杭の位置、種類を確認しましょう。
境界杭がなく売り主が対応しない場合は飼い主が境界杭を自腹で設置する事になります。5-6万円で法務局に登記する手続きを取ります。ただし境界確定測量の代金は高額です。売主が境界確定測量を行ったうえで買い主に引き渡すのが通常です。
また、道路側にある基準点がない場合、その工事会社に復元の義務があるので不動産屋に確認しましょう。
・越境
樹木の枝や建物の一部が越境している場合、法律的にトラブルになるリスクがあります。購入後に発覚すると対処が難しくなるので、事前に現地確認を。測量士や不動産会社への相談も有効です。
境界に越境物があるとローンを通してくれない銀行もあり資産価値が下がります。
庇などが越境している場合、撤去してもらうか建て替え時に撤去してもらう契約書や覚書を交わしておきましょう。木の枝葉は覚書は不要ですが根っこは必要です。エアコンの室外機、物置は不要。雨樋、窓格子、アンテナ、後付けバルコニーは必要と複雑です。
越境に関して私が最も衝撃だったのは↓の事実です😫
ずれている塀や越境物を長年放置しておくと以下の民法により将来その土地をとられてしまいます。
10年間平穏に他人の物を占拠したものは、その所有権を取得する 民法162条
・ブロックの劣化
古いブロック塀は強度が落ちており、地震時に倒壊の危険性があります。倒壊した時の責任は塀の所有者です。外構の修繕費用が別途かかる可能性もあるため、劣化具合をチェックし、必要なら補修や撤去の費用も見積もりに入れておきましょう。所有者には老朽化の際に補修する義務が発生しますので所有者は誰なのかを確認しましょう。
・ブロックの所有権
先述した通り隣地との間にあるブロック塀は、どちらの所有物かを明確にすることが大切です。勝手に改修や撤去ができない場合もあり、トラブル回避のためにも権利関係を購入前に確認しておきましょう。
ブロックが1.2mを超えて補強がない場合、補強は誰がやるのかを確認しましょう。
また、隣と共有で作った塀の場合は厄介なので覚書等がない場合は避けたほうが無難です。
私道

・開発者名義になっていないか?
私道が開発業者の名義のままだと、将来的に権利移転がスムーズに行かないことも。第三者に継承されることがあるため、覚書が交わされているか、将来のトラブルを防ぐ仕組みがあるかを確認しましょう。
勝手な使い方していないか?
私道に家庭の植木や柵などが置かれていると、通行や建築の妨げになります。正式な共有持分があっても、現実的に使えない状態では意味がありません。現地での状況確認が不可欠です。
土地を見に行った際に私道に勝手に車が止められていないかを確認してみましょう。
我が家の前の私道には行動との境目に車が常に止まっています。
車の持ち主は私道横のお宅です。
車が邪魔で子供が見えず危ないです😥
でも我が家の駐車場から少しでも車が出ていると苦情が来るんですよね🤨
ホント早く引っ越したい😑
そんな厄介な私道についても少し深ぼっていきます。
が、正直私の場合、私道がある土地は買いたくないというのが正直なところです🤔
私道の持ち主
私道が絡む土地は注意が必要です。私道があるだけで土地の評価が下がるケースもあり、将来的なトラブルの火種になりやすいため、慎重な確認が欠かせません。
- 所有者の確認が第一歩
先述の通り私道が開発業者名義のままになっていたり、全体を共有している場合でも所有者全員が把握できていないケースがあります。所有権移転登記が完了しているかどうかを確認しましょう。 - 私道の「誰の持ち分か」を必ず確認
自分の敷地が接している公道までの道のりにある私道すべての持ち主(共有持分の比率を含む)を確認します。誰か一人でも不明だと後々の道路掘削工事などの交渉が難しくなります。 - メンテナンス費用トラブルに注意
共有私道でも、たとえば奥の道が壊れたとき、手前の住人が「自分には関係ない」と補修費用を出さないケースがあります。維持費の負担やルールを事前に不動産屋に確認しておくと安心です。 - 小さな改修でも合意が必要
共有名義の私道では、たとえ小規模な工事でも過半数の同意が必要な場合があります。スムーズな合意形成ができる相手かも含めて考慮が必要です。
私道承諾書
私道に接している土地を購入する場合は、必ず「私道承諾書」の取得が必要です。これがないと、建物の建築や車の出入り、ライフラインの引き込みができないリスクがあります。
- 共有か分割かでリスクが違う
私道の権利形態が「共有」か「分割」かで手続きや制約が大きく異なります。特に分割所有では1人でも反対者がいれば工事ができないことも。掘削・通行・管理に関する覚書があると安心です。 - 具体的に必要な書類や確認内容
以下の3点は特に重要です。
① 掘削や管理に関する覚書の有無(例:ガスや上下水道の引き込みなど)
② 所有者が認知症などで署名できない状態に備えた対策
③ 車両通行を許可する「通行承諾書」 - 承諾書の費用や有効性を確認
これらの承諾が無料で取得できるか、契約に明記されているかを必ず確認しましょう。書面の有無によっては、契約を白紙撤回できる旨を特約に入れておくと安心です。 - 取得は不動産業者に依頼
私道に接している場合は、仲介する不動産会社に「私道承諾書を必ず取得してほしい」と依頼しておきましょう。曖昧なまま進めると、後でトラブルになる可能性があります。
前面道路

・車2台がすれ違える幅(4.5m)以上、できれば6m
前面道路の幅が狭いと、駐車や車の出し入れが困難になるだけでなく、工事車両の進入にも影響します。最低でも4.5m、できれば6mあると日常生活のストレスも軽減されます。
4m以下の場合は道路拡張の為、敷地が減らされます。道路課へ確認しましょう。すれ違いする場合は4.5メートルは欲しいです。
また、道路から受ける斜線制限については狭い道路と広い道路で囲まれている場合、狭い道路を広い道路幅とみなして斜線制限される緩和要件があることを覚えておきましょう。
・交通量は多くないか?(子供の安全性)
前面道路の交通量が多いと、子どもの飛び出しによる事故のリスクが高まります。特に小さな子どもがいる家庭では、安全面からも静かな住宅街が望ましいです。時間帯ごとの通行量も確認を。
現地では抜け道になっていないか?振動と音、安全性の確認をしましょう。平日と休日訪れて1日現場にいて確認すると見えてくるものも多いでしょう。また最寄駅から物件まで朝と夜に歩いてみて治安、便利、嫌悪施設、臭い、日当たり、外灯の有り無し、砂埃、雨の日であれば水はけなどを確認してみましょう。
この辺りの確認は購入される土地が遠いと非常に困難です。
現地を確認された際に住民に聞いてみるのも良いと思います。
コミュ力の低い私には到底できる芸当ではありませんが😂
・歩道の有無
歩道が整備されているか?ガードレールなどの設置があるか?今後の工事予定があるかも大切なポイント。歩道があると通行の安全性が高まり、通学や散歩時にも安心です。役所や不動産会社に将来的な道路計画を確認しましょう。
造成

・造成方法
造成の内容次第で、土地の安定性や将来的なメンテナンス費用が大きく変わります。切土か盛土かによっても建築コストに差が出るため、不動産屋へ確認したい重要な項目です。
・埋め戻しをしていないこと(不同沈下を懸念)
以前に地下構造物などを埋め戻して造成された土地は、不同沈下(建物が斜めになる事)のリスクがあります。分譲地などで擁壁を造成するときは必ず埋め戻しをしています。埋め戻しの土は必ず沈下するので1m以上の擁壁には注意が必要です。
高低差が1m未満の場合、高低差の解消を建物の基礎で一部深基礎とする事で対応することもできます。
・残土処分で盛土をしていないこと(無駄に土留めが必要)
残土処分のために不自然な盛土をされている土地は、土留めや擁壁の追加工事が必要になることがあります。道路面に対して土が盛られているため見た目で分かります。購入する時は不動産屋に土留め費用の確認をしましょう。
高低差
・高低差1.5mまで、できれば1m(建築費都合)
隣地との土地の高低差が大きいと、深基礎対応や外構の擁壁に追加工事が必要になり、建築コストが跳ね上がります。できるだけ1m以内に収まる土地を選ぶと、無駄な出費を抑えやすいです。また、高低差があると斜線制限にかかりやすいので注意が必要です。
・傾斜地
前面の道路が坂になっている土地は、一見すると日当たりが良くて魅力的に見えます。特に道路より高い位置にある土地は、明るく開放感があり、プライバシーも確保しやすいのがメリットです。
ただし、その分造成工事や排水処理に手間とコストがかかることも多いので注意が必要です。
費用は土留めで対応できる場合と擁壁で対応する場合では大きく差が出てくるので不動産屋に確認をとりましょう。
傾斜地の注意ポイント
造成費用も要チェック
例えば、50坪の土地に高さ40cmの土を盛ると(道路面よりも敷地が低い場合)、造成費用だけで約80万円かかることもあります。建築費以外の予算として見込んでおきましょう。
雨の日の水はけを必ず確認
現地を見に行くときは、できれば雨の日が理想です。敷地に水が溜まっていないか、水がスムーズに流れているかをチェックしましょう。
道路より土地が低いと水が流れ込むリスク
道路よりも敷地が低いと、雨水が家側に流れ込む危険があります。水はけが悪い土地は湿気やカビの原因にもなるので、避けるのが無難です。
道路より土地が高すぎると駐車場に困る
逆に、敷地が高すぎると車の出入りにスロープが必要になり、駐車場の設計に苦労します。勾配が急だと日常の車の出入りがストレスになることも。
・前面道路の傾斜
平地の前面道路に接する土地
平坦な前面道路に面した土地は、もっとも扱いやすく、建築や外構計画がスムーズです。駐車場やアプローチの設計も容易で、追加工事費も抑えられます。また、排水や土砂対策などの特別な配慮が不要なことが多く、建築コストを予測しやすいのもメリットです。一方で、平坦ゆえに水が溜まりやすい土地もあるため、雨の日の現地確認が重要です。
緩やかな傾斜の前面道路に接する土地
わずかに傾斜のある前面道路に接した土地は、排水の流れが自然に促されるため、水はけの良さが期待できます。日当たりや風通しも良くなる場合が多く、設計次第で快適な住環境を実現できます。ただし、傾斜方向によっては駐車場の設計や土間の高さ調整が必要となるため、設計の自由度やコストに少し影響することがあります。現地では土地と道路の高低差をよく確認しましょう。
急な傾斜の前面道路に接する土地
前面道路に急な勾配がある場合、建築には特別な配慮が必要です。駐車場の出入りが難しくなったり、基礎工事や造成費が大きくなったりするため、想定外のコストが発生しやすくなります。また、大雨時の土砂流出や排水不良にも注意が必要です。現地では、雨天時の水の流れや、土地が周囲より高いか低いかなども確認し、場合によっては水害リスクを検討する必要があります。
・敷地内の高低差
平坦な敷地
敷地全体に高低差がない平坦地は、最も扱いやすい土地です。造成費用が少なくて済み、基礎工事や外構の設計もシンプルです。駐車場の確保や生活動線もスムーズで、家づくりの自由度が高くなります。ただし、まれに雨水がたまりやすいことがあるので、水はけの確認は必須です。特に、周囲より土地が低くなっていないかをチェックしましょう。
道路側が低い敷地
道路より敷地が高いタイプで、いわゆる「ひな壇」形状です。この場合、駐車スペースをつくるために擁壁やスロープの設計が必要になり、外構費用が増える傾向があります。階段や高低差のあるアプローチになるため、バリアフリー性に配慮が必要です。一方で、道路から家が見えにくくプライバシーを確保しやすいというメリットもあります。造成済みかどうかもチェックしておきましょう。
道路側が高い敷地
道路から敷地が下がっているタイプで、建物が道路よりも低い位置になります。この場合、雨水が道路から流れ込みやすく、排水や浸水対策が非常に重要です。また、陽当たりや風通しが悪くなるケースもあるため、日照シミュレーションなどの事前確認をおすすめします。道路との高低差が大きいと土留めや排水ポンプなどの追加工事が必要になることもあるので、コスト面に注意しましょう。
・地形
平坦な土地
全体的に傾きのないフラットな土地は、建物の設計がしやすく、造成費用も抑えられるのが魅力です。駐車場やアプローチの設計もシンプルになり、生活動線がスムーズです。ただし、水が流れにくい地形のため、雨の日に水たまりができやすいことも。事前に水はけの状態を確認しておくと安心です。
南だれの土地(南向きに傾斜)
南側に傾いている土地は「理想的な形」と言われ、陽当たりが良好で人気があります。南面にリビングや庭を設けやすく、冬でも暖かく明るい住まいを実現しやすいです。ただし、敷地の前面が道路より低い場合は、排水対策や土留めが必要になることもあります。
東だれの土地(東向きに傾斜)
朝日をたっぷり取り入れやすい土地です。早起きのライフスタイルや朝型の家庭にはぴったり。日中の直射日光はやや弱くなるため、夏は涼しく感じる一方で、冬場は室温が上がりにくい傾向もあります。プラン次第で快適な住まいをつくれます。
西だれの土地(西向きに傾斜)
午後から夕方にかけて日が入る土地です。特に西日が強く当たるため、窓の位置や庇(ひさし)などで調整が必要です。うまく設計すれば、明るさを活かしつつ、夏の暑さを軽減できます。西向きリビングなどは人によって好みが分かれるため、現地で日照を確認しましょう。
北だれの土地(北向きに傾斜)
北側に傾いている土地は、陽当たりがやや劣るのが難点です。とくに冬場は寒くなりやすいため、断熱や採光の工夫が不可欠です。ただし、夏は直射日光を避けやすく、安定した明るさが得られるというメリットも。庭やデッキを南側に設ければ快適性は十分確保できます。
擁壁

・検査済証の交付を受けているか確認。2m未満は申請で費用が発生しない
土地に擁壁がある場合は、まず「確認申請」や「検査済証」が交付されているかをチェックしましょう。不動産会社からもらう重要事項説明書に記載がない場合は、必ず調査を依頼してください。
たとえ擁壁が2m未満であっても、図面が存在するはずで、正規に作られているかは確認が必要です。
申請や許可がない擁壁は、将来的に建て替えが難しくなるリスクがあるため注意が必要です。
施主系のユーチューバーの方で既存の擁壁の上に新しい擁壁を作ろうとしたところ既存の擁壁に検査済証がなく、一度既存の擁壁を壊してから作業をされていた方がいました。当然費用も数百万かかったとの事だったので用心に越したことはないと思います😅
・1m以下としたい。2mを超えない。
擁壁の高さは、原則2mを超えないようにしましょう。構造的にも、申請の手間や費用の面でも、1m以下が理想的です。2mを超える擁壁は、建築基準法上の「構造物」として特別な申請が必要になり、コストもかさみます。
注意しないといけないのは1mの高さの擁壁を建てた後に1mの擁壁を建てている場合です。
この場合、高さは計2mとなりますが検査済証の無い擁壁になります。
つまり、強度の保証もない擁壁を引き継ぐことになりますので必ず検査済証はもらう様にしましょう。
・擁壁の寿命は五十年。あと何年の寿命?
擁壁の一般的な耐用年数はおよそ50年です。
築年数が古い土地では、擁壁が劣化していないか、あと何年もつかを確認することが重要です。
状態によっては補修費や建て替え費用が必要になる可能性があります。
・水抜き穴がない、亀裂が激しい。
擁壁に「水抜き穴」がないと、水圧がかかって崩壊の原因になります。
また、大きな亀裂やひび割れが見られる場合も要注意。老朽化や施工不良の可能性が高く、補修ややり直しが必要になることもあります。現地を確認される際にチェックしましょう。
・安息角は30度必要だが、確認申請のある擁壁がある場合は不要
建物を擁壁のすぐ近くに建てると、土砂崩れや転倒の危険性が出てきます。
安全のためには、擁壁の内側から30度以上離して建てる(=安息角の確保)が原則です。
ただし、確認申請の通った擁壁であれば、この角度規制は不要な場合もあります。
・基本的には劣化しない?RC擁壁か間知ブロック以外は×
擁壁にはさまざまな構造がありますが、鉄筋コンクリート(RC)製か間知ブロック製のものが最も信頼性が高いとされています。
その他の素材や構造では、劣化が早かったり土圧に耐えられなかったりすることもあるため注意が必要です。
・ブロックを土留として使う場合は3段まで
コンクリートブロックを積んで擁壁のように使う場合、3段までが限界とされています。
それ以上積むと土圧に耐えられず、倒壊の危険があります。
どうしても高くしたい場合は、型枠RCブロックなど構造的に強いものを選ぶ必要があります。
あと、擁壁を外構屋に注文すると強度が不十分な物を提案されるので、擁壁専門業者を入れて見積もりを取ることをおすすめします。
・木を近くに植えると根っこでブロックを破壊する。
擁壁のすぐそばに木を植えるのは危険です。
木の根が成長してブロックを押し壊すことがあるほか、木を抜いた際に土が流れて擁壁が崩壊する可能性もあります。よくアスファルトから木の根っこが出ていますよね?植物の力すごいです😮
植栽計画は擁壁との距離を考慮して行いましょう。
制限

・防火規制や防火設備の有無を確認する
土地が「防火地域」や「準防火地域」に指定されていると、窓や外壁などに防火性能が求められ、建築コストが上がります。加えて設計の自由度にも制限が出るため、「希望する家」がその範囲で実現可能かどうかを、購入前に必ず確認しておきましょう。
防火仕様の設備っていちいち高いですよね😓
・高度斜線やローカルな制限をチェックする
「高度斜線制限」は建物の高さや屋根の形状に影響を与える重要な規制です。その他、自治体独自のローカルルールが設けられている場合もあるため、建築士や行政窓口に相談し、希望する間取りや外観が実現できるか事前に調べておく必要があります。
・雨水浸透施設の設置義務があるか確認する
一部地域では、敷地内で雨水を地中に浸透させる施設の設置が義務付けられています。これにより、建物の配置や庭のレイアウトに制限が出ることも。設計後に想定外の費用が発生するリスクがあるため、必ず自治体の規定と補助金制度を確認しておきましょう。
・建築協定や各種法令の制限を確認する
土地によっては「建築協定」や「宅地造成規制法」など、外観・構造・規模に関する制限が定められています。希望通りの家が建てられない可能性があるため、土地購入前に行政や不動産会社に確認し、法的制限の有無を明らかにしておきましょう。
・小屋裏収納に関する制限を確認する
小屋裏収納は建築基準法によって使用条件が厳しく定められています。固定階段を設置できない、窓の位置が制限される、エアコンが取り付けできないなどの制約があるため、「収納が豊富な家」を検討している方は、事前に法規制をよく確認しましょう。
我が静岡県では固定階段を小屋裏に繋げて良いのでそのように計画する予定です。
そして設計士をも引かせてしまった荷物の量をそこにぶち込む予定です😙
え?断捨離??気が向いたらやります・・・🙄
・用途地域を確認し、周囲の環境を把握する
用途地域によって、建てられる建物の種類や規模が決まります。住宅地と思って購入したら、実は商業地域で近隣に工場が建つ…という事例も。住環境や騒音・においにも影響するため、用途地域、建ぺい率、容積率のほか、周囲の地域種別も地図で調べておきましょう。
※第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さ制限や建物の用途に厳しい制約があります。
・建ぺい率を確認し、希望の間取りが入るか確認する
建ぺい率は「敷地面積に対して建てられる建物の占有面積の割合」を示す指標です。たとえ広い土地でも、建ぺい率が低ければ希望の大きさの家が建てられないこともあります。特に第一種低層住居専用地域では、建ぺい率40%など厳しい制限があるため、希望の間取りが入るかどうかを事前にチェックしましょう。
・容積率を確認する
容積率は「敷地に対して建てられる建物全体の延べ床面積」を制限するものです。2階建てや吹き抜けリビング、大型収納などを希望する場合、容積率が低いと計画通りに建てられない可能性があります。土地を検討する初期段階で容積率を確認し、建てたい家に必要な延べ床面積が確保できるか確認しておきましょう。
私の欲しい土地がまさに容積率が厳しく欲しい部屋が満額で置けなさそうです。
トレーニングルームだけは無くしたくない。。。😥
その他追加費用

・電線 鳥の糞被害。電線の防護管がクレーン作業で必要。
電線の真下は鳥のフン被害が発生しやすく、外壁や車が汚れる原因に。また、クレーン作業時には防護管の設置が必要になり、意外な費用(20-30万円)が発生することも。配置計画や予算に影響するので事前確認を。
・電柱 将来設置される?電柱が近くにない場合、中継ポールを立てる
電柱が近くにない土地では、引き込みのために中継ポールの設置(20-30万円)が必要になり、その費用は自己負担になるケースもあります。将来の設置予定も含め、建築会社を通して電力会社に確認しておきたい点です。
・変圧器 太陽光パネルを積んでる家が沢山ある?電柱の変圧器を変える?
周囲に太陽光発電の家が多いと、電柱の変圧器の容量が不足し、新築時に変更が必要な場合があります。電力供給に関するインフラ整備に予想外のコスト(40-50万円)がかかることがあるので、こちらも建築会社を通して電力会社へ要確認です。
・道路標識 将来設置される?可能性を確認する
目の前の道路に標識が新設されると、視界や動線に支障が出たり、デザインの自由度に影響が出ることも。特に角地や幹線道路沿いでは注意が必要で、将来の設置計画も念のため調べておくと安心です。
・切株 切り株の撤去に10万
一見なんでもない切り株でも、撤去には重機が必要で10万円前後の費用がかかることもあります。土地価格だけでなく、こうした「埋設物」による追加費用も含めて、現地でしっかり確認を。
切株ではないですが大型分譲地でも岩盤撤去で200万等請求(※)されることもあります。
(※)瑕疵担保保険は適用されないのか?
大型分譲地であっても岩盤撤去などの追加工事費が数十万円〜数百万円発生するケースはあります。そして、基本的にはその費用は買主(施主)負担になることが多く、瑕疵担保保険(住宅瑕疵担保責任保険)ではカバーされません。
うーん、この費用負担は厳しいですね😣
瑕疵担保保険(住宅瑕疵担保責任保険)の対象ではない理由
住宅瑕疵担保責任保険は、以下のような「引き渡し後の構造的な欠陥」に備える保険です。
- 基礎や柱、屋根などの構造耐力上主要な部分
- 雨漏りなどの雨水の侵入を防止する部分
したがって、
地盤や地中障害物に関する費用(岩盤・廃棄物・埋設物など)には原則適用されません。
また、瑕疵担保保険以前の問題として、「岩盤が出る可能性がある」と事前に説明があった場合は売主や施工業者に責任はなく、買主負担になるのが通常です。
対策としてできること
- 契約前に地盤調査データを確認する(あれば近隣区画のものも)
- 地盤改良や岩盤撤去の「追加費用が発生する可能性があるか」を不動産業者・工務店に質問する
- 「地中障害物の撤去費用は誰が負担するのか」を契約書で明記してもらう
- 万が一に備えて、地中埋設物保証や独自の保証制度を設けている会社を選ぶ
隣地の状況

・水はけ(降雨の翌日に確認)
隣地の水はけが悪いと、雨のたびに自宅の敷地までぬかるみや湿気が流れ込む可能性があります。見学時が晴天だと気づきにくいため、できれば雨の翌日に現地を確認すると◎。湿ったままの地面は、将来的なカビや基礎への影響も見逃せません。
またまた施主系ユーチューバーのお話で、庭の排水がうまくいかず、プール状態になっているお宅を見たことがあります。その方は自力で排水工事をしていましたがかなり大変そうでした😨
・消火栓(消火栓の前に車庫は建てられない)
意外と見落とされがちなのが消火栓の位置。自宅の目の前にあると、駐車場や車庫を設置する際に制限を受けることがあります。設計の自由度を大きく左右するため、配置計画に支障が出ないか必ず確認を。
・外灯(公園等の外灯が直撃しないか?)
隣接する公園や道路の外灯が、自宅の寝室やリビングを直撃していた…なんてケースも。夜の明るさは住み心地に直結します。夜間にも現地を訪れて、光害がないか確かめるのがベストです。
・換気扇や室外機、湯沸かし器などの音・臭い
隣家の設備から発せられる「低音のゴーッという音」や「排気臭」は、静かな住宅街でこそ気になります。日中は気づかなくても、夜は特に響く場合も。風向きや配置も含めて注意して観察を。
・外灯が寝室を直撃していないか?
隣家の外灯が、あなたの寝室や子ども部屋の窓を明るく照らしていると、カーテン越しでもまぶしく感じることがあります。夜に照明がどの方向を向いているかも要チェックです。
こちらの外構計画でもお隣さんに迷惑のかからない外灯計画を心掛けたいですね😄
・圧迫感のないフェンスか?
隣地との境界に設けられたフェンスや塀が高すぎたり、黒色だったりすると、日当たりや心理的な閉塞感の原因に。建築前から圧迫感を感じるようなら、その土地は慎重に再検討を。
逆にこちらがフェンスを設ける際には採光性や圧迫感を配慮しましょう。
近隣トラブルは全力で避けにいきましょう😉
・隣地を利用することが前提になっていないか?
駐車場の乗り入れなどで隣地を利用することが前提となっている場合、隣人が変わったり一方が車を利用しなくなったときにクレームがきます。特に、車を使わないご近所さんほど、車の動線や騒音には敏感です。
・空き家(空き家の隣は買わない。更地にする予定という話は嘘の可能性あり)
「更地にする予定」と説明されていた隣の空き家が、いつまでたってもそのまま…なんてことも。古くて手入れされていない家は、防犯面や景観にも悪影響を及ぼします。売主や仲介の言葉が嘘の可能性があります。現況重視で。
・古家(取り壊しにはアスベストや隣家との問題がある)
2006年9月1日以前に建てられた古家は、アスベスト調査が義務です。
売主が調査済かどうか必ず確認しましょう。
もし「していない」と言われたら、買主側で調査費用を出してでも依頼するべき。契約申込書にその旨を明記し、調査を拒否する売主とは取引しないのが原則です。
万一アスベストがあれば、解体費用が200万円以上追加になる場合も。事前に見積もりを必ず取っておきましょう。
・線路の近く(鉄粉で洗濯物が汚れる)
線路が近いと音の問題に目が行きがちですが、実は「鉄粉」による洗濯物の汚れも厄介です。屋外干し派にとっては死活問題。鉄道の種類や距離によって影響度は変わるため、現地で洗濯物が干されているかを確認するのがおすすめです。
・心理的瑕疵(事件歴の有無を確認)
その土地や建物で過去に事故や事件があった場合、「心理的瑕疵あり」とされ、資産価値が下がったり、ご近所との関係に影響が出ることも。不動産業者には告知義務があるので、必ず確認しましょう。
気になる場合は「大島てる」などの事故物件情報サイトで自主チェックを。
なお、事故物件は「2人目以降の入居者」には説明義務がないため、事前確認は自己防衛にもなります。中には、1人目の入居者となって告知履歴を削除する専門業者が関わっているケースもあるので要注意です。
・告知事項(重要事項説明書を確認する)
土地や建物を契約する際には、「重要事項説明書」という書類に注意点がまとめられています。過去のトラブル、建築制限、境界問題などが記載されていることも。
「聞いてない…!」とならないよう、契約前に説明をしっかり聞いて、自分でも内容をよく読みましょう。納得できない点があれば、遠慮せず質問を。
重要事項説明書は契約の1週間前にもらって熟読しておきましょう。
特に最後の特記事項は事前にわからない事や対応を調べておきましょう。
インフラ

安全性に関しては前回の記事にて説明をしたので次はインフラです。
・上水道(工事の必要性)
土地によっては、上水道の引き込み工事が必要なことがあります。費用は数十万円かかることもあり、道路の掘削や役所の許可が必要な場合も。
購入前に水道メーター(量水器)を開けて「20」と書かれていれば工事不要の可能性が高いですが、「13」など古い規格だとやり直しが必要なことも。必ず現地でチェックを。
・下水道(工事不要か?配管が隣地の地下を通っていないか?)
下水道が整備されていても、あなたの土地に直接つながっていなければ接続工事が必要です。また、排水管が隣の土地の下を通っていると、後々のトラブルの原因に。上水道にも同じことが言えますが水漏れしても相手の土地の掘削許可が出なかったり、フェンス、土間を壊して復旧しないといけないなど心配事が絶えません😥
下水が通っていないエリアでは、浄化槽が必要で設置費用が50〜70万円ほどかかりますが、自治体によっては補助金が出ることもあります。
・電気(ソーラーパネル10kW設置を考えている場合)
将来的に10kW以上の太陽光発電を載せたいなら、土地に面した電柱の設備も要チェックです。容量不足だと、変圧器の交換などで数十万円かかることも。
発電システムの規模が大きくなるほど電力会社との調整も複雑になるため、計画段階から確認を。土地購入後に想定外の出費にならないよう、事前に問い合わせておくと安心です。
・側溝などの追加工事(追加工事が発生しないこと)
土地によっては、側溝や排水路の整備が不十分で、購入後に造成や補修工事が必要になるケースがあります。家の前に側溝が無い場合、側溝を作る必要があります。道路の反対側に側溝がある場合、排水のために道路を掘削することになると工事費は約60万円、縁石の撤去も10万円ほどかかります。
現地で「側溝がどこにあるか」「道の反対側にあるか」を確認し、必要ならハウスメーカーの担当者に費用見積もりや土地価格交渉を依頼しましょう。
・都市ガス
将来的にガスを使いたい場合は、その土地に都市ガスが引き込めるか事前確認を。
都市ガスが利用できれば、プロパンガスよりもランニングコストを抑えられることが多く、長期的な生活コストに差が出ます。近隣の家に都市ガスのメーターやガス栓があるかを確認し、不明なら不動産会社に問い合わせを。
・ゴミ捨て場(近いか?10m以内か?臭いが来るほど隣接?角地に置かれがち)
ゴミ置き場が家のすぐ前にあると、においやカラス被害、景観の問題が発生しやすくなります。
角地や目立つ空き地などには設置されやすいため、現地で「ゴミ捨て場がどこにあるか」「自宅からの距離はどれくらいか」をチェックしましょう。
既に場所が決まっている場合は、管理状態やご近所とのトラブルがないかも不動産会社を通じて確認をしてみるのも良いです。
ごみ集積所とコンビニのトイレはその土地の民度を表すそうなので要チェックです😉
環境

周辺隣人、自治会
・近隣調査を希望(危険人物、変わった人、隣人トラブルはないか?)
どれだけ理想的な土地でも、隣人とのトラブルがあれば快適な暮らしはできません。購入前に近所を散歩したり、不動産会社や工務店に「ご近所トラブルはなかったか」具体的に質問してみましょう。
できれば、自分でゴミ出しの様子や町の雰囲気を観察して、住みやすい環境か感覚的に確かめるのも有効です。
私の様なコミュ力の低い同士は「トナリスク」や探偵などの調査サービスを使う方法もあります。コンビニのトイレやゴミ箱の使われ方、交番での犯罪件数の確認も地域の民度を知る手がかりになります。
不動産屋は悪いことを言わない傾向があるため、質問の内容を事前に決めて聞くと良いです。

またまた施主系ユーチューバーの話ですが、お隣さんが平気で越境してくる人で敷地内に越境物を戻すと嫌がらせをしてくるような人だったという動画を出されていました。
私はコメントで「土地購入前にあいさつに行って様子を探らなかったんですか?」と聞いてみると「挨拶をした旦那さんは良い人で、問題は奥さんでした。挨拶に出てこなかったのでわかりませんでした」との事でした。その方は裁判に持っていくとの事でした。
これは極端な話ですが、私も近隣に嫌な人がいるのでこの項目の優先度はかなり重要視していて土地の立地や条件よりも優先しています😣😣😣
・強制参加のイベントがないか(自治会、町内会の活動内容)
地域によっては、祭りや地域清掃、定期的な集会などの行事が「暗黙の了解」で強制参加になっていることもあります。共働きや小さな子どもがいる家庭では、負担が大きく感じられることも。
地域の自治会にどんな行事があるか、実際に近所の方に聞くか、不動産会社を通じて事前に確認しておくと安心です。
私の会社の友人は年30回ほど子供会の準備をする係になってしまいました。
まじで恐ろしいことだと思います(個人の感想😅)
・役員の決め方は?(新しい人に役員になってもらうこともある)
「引っ越してきた人が順番で役員になる」というルールがある地域では、入居直後に役職を任されるケースもあります。
年1回の持ち回り程度ならともかく、祭りやイベントの仕切り役になるとかなりの負担に。
役員の選出方法や頻度は、自治会や近所の方にしっかり確認しておきましょう。
私は現在賃貸(一軒家)に住んでいて新築を計画中ですが、借家なのに組長役が回ってきたりします。
ご年配の方が多い地域なので「私はもう組長、役員とか出来ない」との事で異常にローテーションが速いです。勘弁してほしいです😥
・地域の独自ルールがないか?(朝8時半以降にゴミ出し等共働き対応不可)
地域によっては「ゴミ出しは朝8時半以降」などの独自ルールがあり、共働き家庭には対応が難しい場合があります。
ゴミ出しの時間やルールが柔軟かどうか、役所や近所の人に確認しておくと、暮らしやすさの目安になります。ゴミ出しに関しては以前の記事にある通り私の地域は資源回収当番は7時間棒立ちしないといけない異常地域です。変なルールが無いかは絶対に確認しましょう😅
・町内の掃除当番は有給使う必要がある?
地域によっては、平日の午前中に町内清掃が行われ、有給を取らないと参加できない場合もあります。
掃除当番の頻度や免除の条件などを、自治会や近隣住民にあらかじめ確認しておけば、入居後のトラブルやストレスを防げます。
またまた私の地域の話ですが、不参加の場合は1000円の罰金を払わないといけないです。
早く引っ越したい😥
・土地を売った理由は何か?(近所トラブル?内容によってはNG)
売却理由がはっきりしない土地には注意が必要です。たとえば、「ご近所との関係が悪化した」などの理由だと、同じ問題に巻き込まれる可能性もあります。
不動産会社には「なぜ売るのか?」「いつから売りに出ているのか?」「境界は明確か?」など、気になる点は具体的に聞いてみましょう。答えがあいまいな場合は、慎重に検討を。
・地域や自治体の掲示板に掲載されている内容で面倒ごとはないか
掲示板には、地域住民の苦情や注意喚起が書かれていることが多く、日常のトラブルの有無を知る手がかりになります。
「騒音注意」「違法駐車への苦情」などの掲示が頻繁にある地域は、住民同士のトラブルが多い可能性も。現地に足を運んで掲示板を確認するだけでも、地域の民度がわかります。
周辺施設

・騒音 夜は静かか?幹線道路など。平日、休日、どの時間でも
昼間に静かでも、夜や週末に騒音が増える場所もあります。幹線道路や繁華街が近いと、深夜でも車の音が気になることもあるため、平日・休日・時間帯ごとの音環境を確認しましょう。
現地では工務店のトラック置き場から発生する騒音や橋のつなぎ目を通るトラックのガタガタ音などが気にならないかを確認しましょう。
私は高架橋の横のマンションに住んでいたのでつなぎ目の音が大きかったのは覚えていますが気になるタイプではなかったようです😁
・隣接道路の車通りが少ないか?
前面道路の交通量が多いと、車の出入りが難しく、子育て世帯には特に不安要素になります。安全な住環境を確保するためにも、日中の通行量を実際に現地で確認しておくのが安心です。
・駅までの外灯
夜間の帰宅時、駅から自宅までの道に外灯が少ないと、防犯上の不安があります。特に女性や子どもの通学路として使うなら、暗い道がないかどうかを事前に確認しておきましょう。
また外灯が敷地を直撃してないか?公園横は街灯が夜直撃しないか確認しましょう。
光害があると睡眠の質が下がります。
・道路、工場の建設予定(今後の騒音、道路渋滞)
将来的に工場や幹線道路の建設が予定されているエリアでは、静かな今とは違う環境になるかもしれません。市役所などで都市計画を調べ、将来の住環境がどう変わるかも把握しておくべきです。
・道路族
周辺の子どもが道路で遊んでいたり、親が路上で長時間立ち話をしている「道路族」がいると、車の出し入れや騒音トラブルの原因になります。平日・休日の様子を観察して判断しましょう。
・将来影を落とす建物が計画されている
近隣に高層マンションなどの建設計画があると、日照や眺望に大きな影響が出る場合も。市の都市計画課などで確認し、将来的な「影のリスク」がないかどうかを事前に調査しておきましょう。
嫌悪施設

・ドブなどの臭い、蚊の発生
敷地周辺にドブ川や水たまりがあると、悪臭や蚊の大量発生につながることも。夏場は特に生活の質を大きく下げる原因になるため、雨上がりや夕方に実際のにおいや虫の発生状況を確認しましょう。
・ガソリンスタンド、工場
近隣にガソリンスタンドや工場があると、生活環境に悪影響が出ることがあります。騒音・排気臭・トラックの出入り・夜間の稼働状況などをチェックしましょう。
土壌汚染(※)のリスクも高いため、過去に工場やクリーニング店、ガソリンスタンドがあった土地かどうかも調べておくべきです。
(※)土壌汚染のリスクと調査の重要性
一見きれいに見える土地でも、過去に工場やクリーニング店、ガソリンスタンドなどがあった場所では、土壌汚染が潜んでいる可能性があります。実際、世界の土壌の約3割が汚染されているとされ、先進国ではさらに高い割合です。
雨水により地下の薬品が地表に染み出すこともあり、土地を掘削した際に薬品のにおいを感じる場合は要注意です。汚染された土壌では、地盤改良材が正常に固まらず、住宅の安定性にも影響する恐れがあります。
購入前に必ず以下の方法で確認しましょう。
- 図書館の古地図や法務局の登記簿で、過去にどのような施設があったかを調べる。古地図は前回の記事の通りネットで調べられるので便利だと思います。
- 担当者の説明だけでなく、登記事項証明書や閉鎖謄本で「作業場」や「工場」などの記載がないか確認する
- 周辺住民や不動産会社に聞き込みを行い、かつて廃棄場などがなかったかを把握する
- 自治体の環境課に問い合わせると、指定工場周辺の土壌汚染リスクがわかることもあります
疑わしい場合は、約20万円程度の簡易調査で汚染の有無を確認可能です。もし汚染されていた場合、数百万円規模の土壌入れ替え費用が発生することもあります。
また、売主は瑕疵担保責任を問われる可能性があるため、買主が希望すれば調査に応じるのが本来の姿勢です。健康被害や土地価値の下落にも関わる重要事項なので、客観的なデータで納得してから契約することが非常に大切です。
・電波塔、高圧線
電波塔や高圧線が近いと、景観や心理的影響だけでなく、健康面への不安を感じる方も。特に小さなお子さんがいる家庭では避ける傾向があるため、将来の資産価値にも影響します。
・火葬場、墓地
火葬場や墓地の近くは、心理的に気になる人が多く、敬遠されがちです。夜間の雰囲気や視界に入るかどうかを確認することで、入居後のストレスや来客時の印象も防げます。
・パチンコ、カラオケなどの騒音施設

パチンコ店やカラオケボックスが近くにあると、深夜まで騒音や人の出入りが続くことがあります。静かな住環境を求めるなら、昼夜問わず現地で音の状況を確認することが大切です。
・飲食店などの臭いが出る施設
焼き肉店や中華料理店などの飲食店は、換気扇からのにおいが風向きによって住宅に届くことも。においに敏感な方は、営業中の時間帯に現地確認をしておくと失敗が防げます。
・反社事務所
暴力団関係など反社会的勢力の拠点が近くにあると、治安面で大きな不安材料になります。外見では分からないことが多いため、事前に不動産会社や地元の人に聞き取りをしておきましょう。
・汚水処理場
汚水処理場が近いと、風向きによっては強烈なにおいが漂うことがあります。特に湿気の多い時期は顕著に感じやすいため、においが届く距離にあるかどうかを地図や住民への聞き込みで確認を。
・臭いの出る畑 聞き込みしてもらう
肥料や堆肥を多く使う畑があると、特に夏場に強烈なにおいが発生することがあります。地元の農家がどのような資材を使っているかは、仲介業者に聞き込みを依頼するのが確実です。
・養豚場、養鶏場、牛舎 聞き込みしてもらう
畜産施設からは、風向きや距離によって日常的に強いにおいが届くことがあります。見学だけでは分からないため、近隣住民から実際の生活感を聞いてもらうよう仲介業者に頼みましょう。
地区によっては悪臭規制防止法が適用されているので、市町村のHPで確認してみましょう。
私も6月付近になると臭いだす地区を知っていますがそこには住めないと思います🤢
・夏場に蚊やコウモリの発生がないか?
近くに雑木林や池、ドブなどの水場があると、夏場に蚊が大量発生しやすくなります。また、蚊を狙って夕方以降にコウモリが現れることもあり、屋根裏や壁の中に住み着くと駆除が大変です。実際に私の家でも、コウモリが壁の中でごそごそ動き回り、夜に(嫁が)寝れなくて非常に困りました😢
害虫対策の手間や健康被害を避けるためにも、夏の夕方に現地を訪れ、様子を直接確認することをおすすめします。周辺環境をよく観察しておくと後悔を無くしましょう。
・学校が近い場合、グランドの土埃などが来ないか?
小学校や中学校が隣接していると、体育や部活動の際にグラウンドの土埃が舞い込むことがあります。洗濯物への影響やアレルギー対策のためにも、風向きと距離の確認は重要です。
・ごみ処理場の近さや臭いの影響はないか?
ごみ処理場が近いと、においや大型車両の出入りが生活に影響することがあります。資産価値にも関わるため、処理場の場所や距離は必ずチェックしておきましょう。
また、臭いはごみ処理場だけでなく、季節や風向きによって牛舎や食品工場などからも漂うことがあります。実際、10km離れた牛舎のにおいが届くケースもある様です。さらに将来的に新しい施設が建設される可能性もあるため、都市計画図を確認し、地元の人にも聞き取りを行うと安心です。
後から「こんなはずじゃなかった」とならないよう、今と未来の環境をセットで調べる意識が大切です
・その他嫌悪施設(臭い施設 5km圏内、その他 200m圏内)
明確な基準がないからこそ、視覚・聴覚・嗅覚に影響する施設は「生活に支障がない距離か」を自分の感覚で確かめることが重要。地図だけで判断せず、現地で歩いて体感することが大切です。
まとめ|ここまで読んでくださったあなたへ

ここまで読んでくださったあなたは、間違いなく「後悔しない土地探し」を本気で目指している、非常に勉強熱心な方だと思います。土地選びは「一生に一度」とも言える大きな決断ですが、その裏にはたくさんの見落としがちなリスクや注意点が潜んでいます。
しかし、この記事で取り上げたように、「事前に知っておくだけ」で防げるトラブルや、「少し調べておくだけ」で何百万円の損失を回避できるケースも多くあります。
騒音や臭い、土壌汚染のリスク、周辺環境、測量図の違いなど、一つひとつを丁寧に確認していくことが、後悔のないマイホーム計画の第一歩です。
ここまで丁寧に読み進めてくださったあなたには、ぜひこの知識を自信に変えて、自分らしい土地選びを進めていただけたら嬉しいです。
最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました!
追記:Note有料記事を作りました。
この記事に紹介したファイルはこのNoteでダウンロードできます。
冒頭に紹介したHM、地元工務店の価格比較の記事です。
各社の特化記事です。