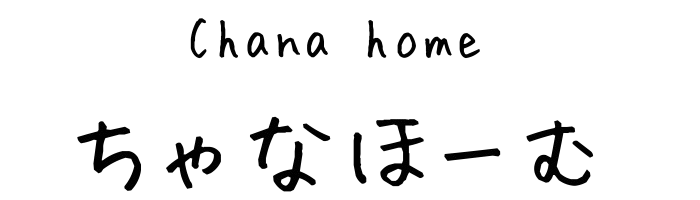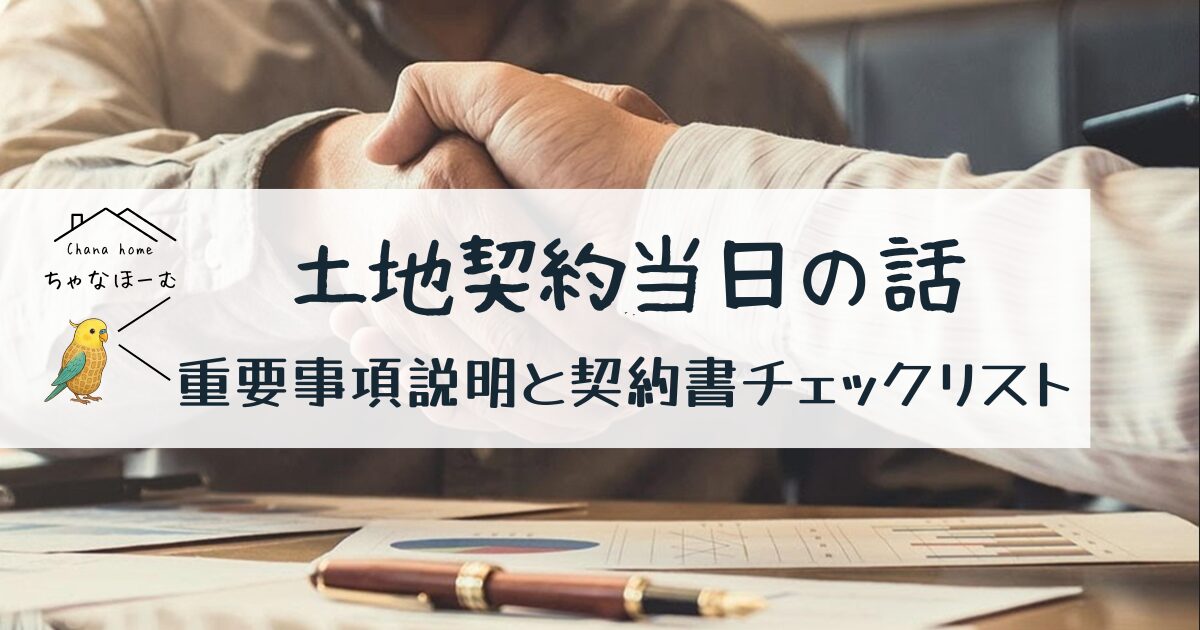契約書に“違約金20%”って書いてあってドキッとしました。これって契約後にすぐに適用されるんですか?

私も驚きました。でも実際には、どのタイミングで発生するのか不動産屋へ確認する事が大切だよ
「この契約内容で本当に大丈夫?」土地購入の契約書や重説を前に、そう感じたことはありませんか?
曖昧な理解のまま進めると、登記や固定資産税の支払いで思わぬトラブルになることもあります。
そこで本記事では、実際の契約で確認した疑問点と、その回答をもとに整理したチェックポイントをご紹介。
具体例を交えながら解説しているので、契約内容を自信を持って判断でき、将来の不安を未然に防ぐことができますよ😀

この記事を読んで分かること
- 土地購入に伴う 登記手続きの流れ(分筆・表題・所有権移転・抵当権設定・抹消)
- 固定資産税の減税措置や公租公課の負担時期 など、誤解しやすい税金の扱いと注意点
- 契約書に記載される 特約条項・違約金・維持管理の義務 をどう理解し、どの程度リスクを受け入れるべきかの判断基準
- 不動産会社に直接確認した具体的な回答に基づく、安心して契約を進めるための実践的なヒント
説明の順序について

いよいよ土地の契約書にハンコを押す日がやってきました。
「ここまで来たらもう後戻りはできない…」という気持ちで、正直かなり緊張しました😅
事前に「重要事項説明書」と「契約書」を読み込みました。
※重要事項説明書とは、不動産の所在地や面積、法的な制限、ライフライン状況、契約解除の条件などを宅建士(宅地建物取引士)が説明する義務のある文書です。
もちろん何度も目を通しましたが、それでも不明点はいくつか残っており、「本当にこのまま進めて大丈夫かな」と不安もありました。
それでも当日は大きなトラブルもなく、無事に契約を終えることができました。
今回の記事では、私自身の当日の体験談をもとに、良かった点と反省点をまとめます。
振り返ってみると「もっと事前準備をしておけば安心できた」と思う部分もあったので、同じように契約を控えている方に向けて、改善点や具体的な準備方法もあわせてお伝えしたいと思います。
不動産取引では、重要事項説明書(以下、重説)の説明が契約書より先に行われることが法律(宅地建物取引業法)で定められています。
重説と契約書には共通する内容が多いため、チェックするときはまず重説から確認するのがおすすめです。
私は最初に契約書の方に疑問点を書き込んでしまい、当日かなり困りました(反省点です)
- 契約当日、まず重説の説明を受ける段階で疑問点が出てくる
- 「あれ、この疑問は契約書に朱書きで書いたんだっけ?」と混乱する
- 重説の説明中に契約書をめくることになり、どこを説明しているのか分からなくなる
- 本番で慌ててしまう
これは私自身が実際に体験した失敗でした。
そのため、疑問点は重説から書き出すことを強くおすすめします。
契約前に準備しておきたいもの
重説と契約書をチェックする際には、契約の1週間前には必ず両方の書類を受け取ることが大切です。事前準備が無かったら小心者の私は当日更に焦ることになっていたと思います😂
準備についてはこの記事を参考にして下さい。
重説で議論になったポイント
共有設備の税金について
私たちが購入したのは14区画の分譲地ですが、すでに住宅が建っていて開発済のお隣の33区画の分譲地と合流するという形で扱われる土地でした。
分譲地には「全体の3%を公園にする」「貯水池を設ける」といったルールがあり、これらの施設を区画ごとに分担して所有・管理する形になります。
そのため私は「これらの共有設備に対して、自分の持分1/14の固定資産税が発生するのでは?」と疑問を持ちました。
結果としては、共有設備に対しては固定資産税はかからないとの説明を受けました。
将来にわたっての支払い問題(払う人vs払わない人)が無いようで安心しました😄
測量図に関する不安
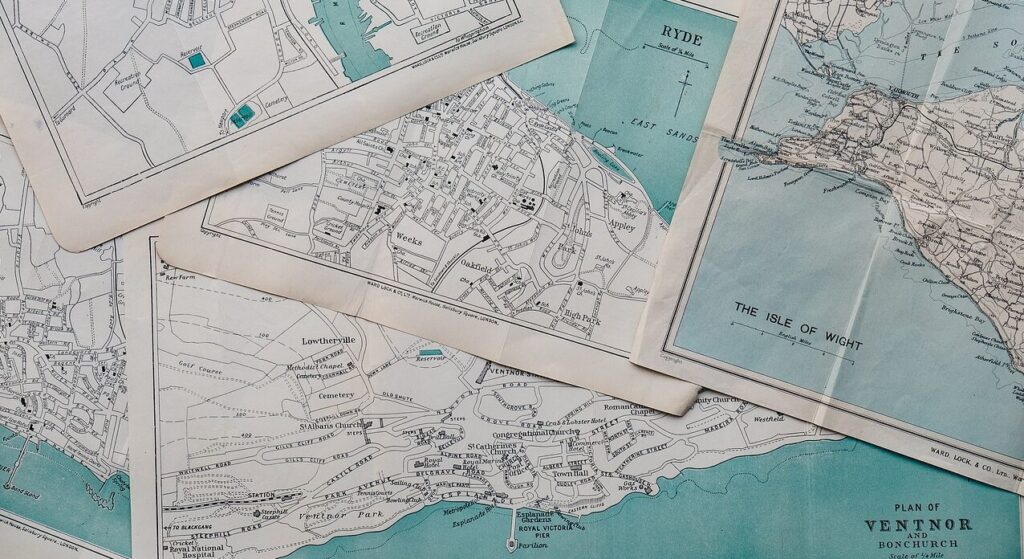
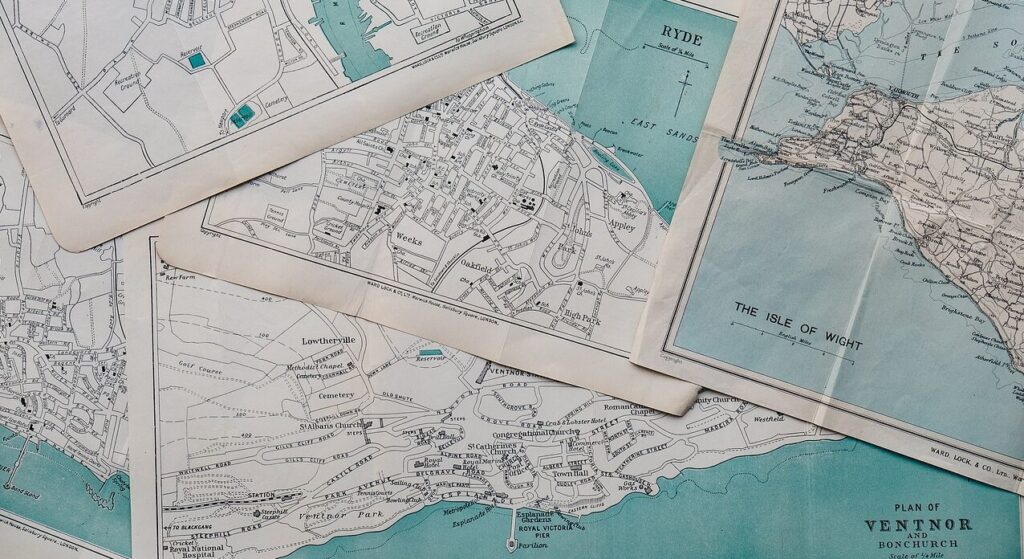
契約書には「確定測量図」ではなく「地積測量図」にチェックが入っていました。
- 確定測量図:隣地所有者や行政と境界を確認し合意したうえで作成された図。境界が法的に保証される。
- 地積測量図:土地の面積や形状を示す図。境界確認を伴わない場合もあり、法的な効力は確定測量図より弱い。
私はネットで「地積測量図では境界線が保証されない」と見かけ、不安を感じました。
そこで質問したところ、不動産会社からは以下のような説明がありました。
- 現在はGPSを用いた測量でXY座標系に基づいて作成されているため、境界の復旧は可能
- 地震などで境界がずれた場合でも、法務局に登記されている地積測量図が法的証拠になる
ネットでは「座標だけでは線が引けない」といった情報もありましたが、不動産会社からは「そのようなことはない」と説明されました。
なぜなら隣の土地も分譲開発された土地なので同じ地積測量図が法務局に登録されているからとの事でした。
厄介なのはお隣さんが違う時期に取得された土地で違う地積測量図が法務局に登録されている場合です。
この場合、こちらがGPSで精度の良い地積測量図を持っていても境界を決める法的な根拠にはなりません。それだけでは相手が主張する境界を否定する事は出来ません。必ず確定測量図を不動産業者に要望してください。
私の土地の場合


私たちの土地は東南北の角地で、それぞれの境界の状況は以下の通りでした。
造成の進捗は上の写真の通りです。
(最初はただの原っぱでしたが境界が出来てきました😀)
- 北側:分譲地の境界確定測量図で隣地所有者と合意済み
- 東側:市道との境界確定測量図で市と合意済み
- 南側:将来的に市道になる予定の開発道路 → 地積測量図
- 西側:隣地との境界 → 地積測量図
つまり、一部は確定測量図で保証され、一部は地積測量図という形でした。
分譲地ですが角地となると複雑なようです😅
こういった事は確認しておき、書類は引き渡し時にもらうようにしましょう。
ネット情報と実際の違い


ネットで調べた情報は、前提条件が不明確な場合が多いと感じました🤔
おそらくネット上で問題とされている案件はGPS測量が普及する前に作成された古い地積測量図を前提としたものも多いのでしょう。
そして先述した通りビビりな私は次の文言でビビります😨
法務局に登記されている座標は「自分側の主張」であって、隣地の合意がない場合は法的に境界が確定するわけではない。
この一文には正直かなり不安を覚えました。
とはいえ、これも先述した通り大規模分譲地では一斉に地積測量図を作成・登記するため、隣地と私の座標は同じになります。結果として、境界をめぐるトラブルの可能性は低いと分かり安心しました。
もし確定測量図が無いが地積測量図のみ有る土地を検討している場合は、不動産会社に依頼して隣地の地積測量図を取り寄せてもらい、座標を照合してもらうのがよいと思います。
座標が違う場合は確定測量図を不動産屋に作成する様に依頼しましょう。
座標(世界測地系)について


- 世界測地系とは、地球全体を基準にした測地システムのこと。GPSや衛星測量で使われる。
- 日本では2002年以降、基本測量や公共測量はすべて世界測地系に統一されている。
つまり、2002年以降に作成された地積測量図であれば、精度の高いものと判断できるそうです。地積測量図の作成年月日を確認しましょう。古い場合は再作成の依頼を出すのをおすすめします。
根抵当権の設定について
契約時点で、その土地には「根抵当権(ねていとうけん)」が設定されていました。
何それ?おいしいの?
そんな訳で不動産屋に聞いてみました。
- 抵当権:借金の担保として土地や建物に設定される権利
- 根抵当権:あらかじめ一定の金額を限度として、その範囲内で借りたり返したりできる担保権
不動産会社が銀行から1億4千万円の枠で借入をしており、その担保として土地に根抵当権を設定していたということです。
私は「引き渡しの時点でこの根抵当権はちゃんと外れるのか?」と心配しました。
説明によれば、契約書に「引き渡しまでに根抵当権を解消する」と記載があるため問題はないとのことでした。
そもそも根抵当権が残ったままでは、私たちが住宅ローンを組めないそうです。
根抵当権が外れた後に土地が我々に引き渡され、その後、私たち自身が住宅ローンを借りる際に、銀行のために抵当権設定登記を行うことになります。
これは司法書士によって手続きされるとの説明でした。
それにしても14区画を1億4千円で購入したという事は、1区画当たり1000万。1800万で購入した土地なのでやはり分譲地は割高ですね😨
土地代が抑えられる田舎で良かった😁
今後の登記の流れ
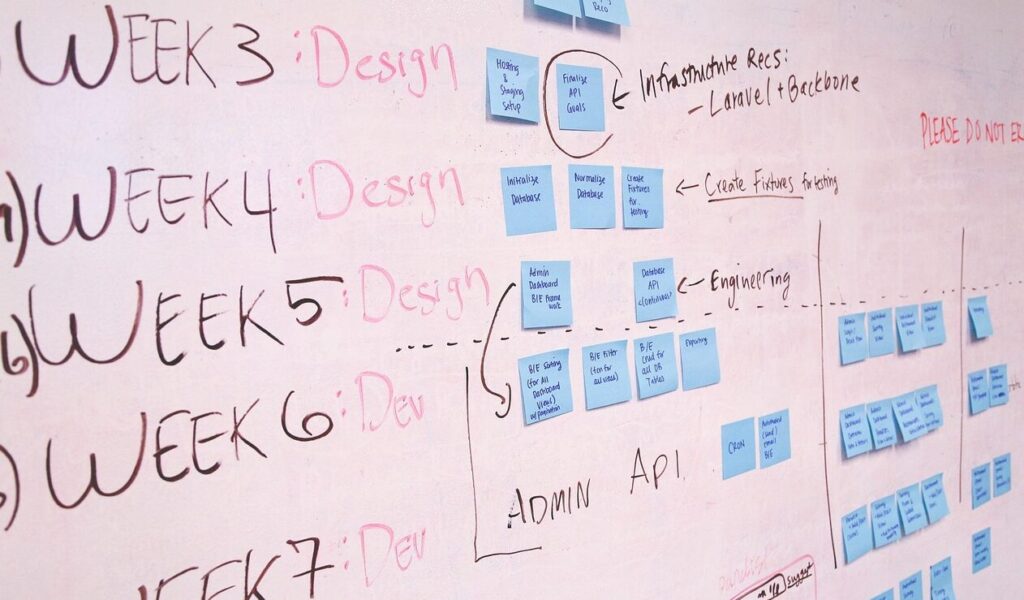
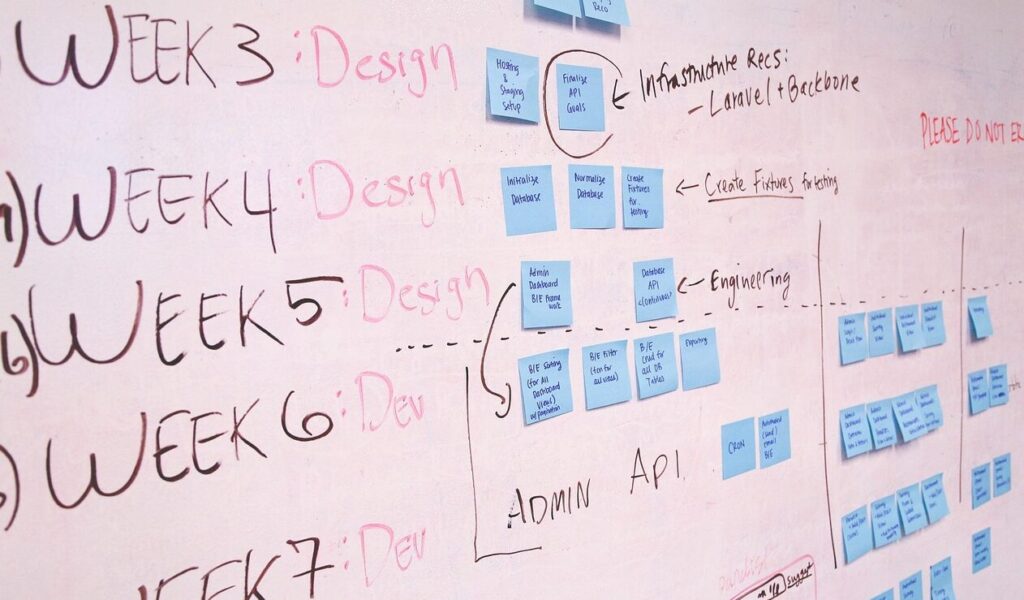
登記に関しては複雑でしたので確認をしました。
登記手続きにはいくつかの段階がありますが、私たち買主が実際に関わるのは次に示す④〜⑥ です。複雑なので備忘録の意味で最後にリストにしておきました😅
④は不動産会社、⑤は銀行側の指定で進みます。
⑥は少し先の話ですが、ローンを完済した後に自分で行う手続きです。
① 分筆登記(表示登記)
- 目的:1筆の土地を複数に分け、新しい地番を付ける。
- 担当:土地家屋調査士(測量士のように専門資格を持つ人)が測量と申請を行う。
- 結果:分けられた土地ごとに新しい登記簿が作成される。
② 表題登記(表示登記)
- 目的:分筆された土地の物理的情報(地番・地積・地目など)を初めて登記簿に記録する。
- 担当:土地家屋調査士
- 義務:不動産登記法で、所有者が一定期間内に申請することが義務付けられている。
- 注意点:この登記がなければ法務局に土地が存在すること自体が認識されず、次の所有権移転登記ができない。
③ 所有権移転登記
- タイミング:売買契約後、代金の支払いと同時または直後に行われる。
- 目的:売主から買主(私たち)に所有権を正式に移転する。
- 注意点:この登記が完了して初めて「土地の法的な所有者」となる。
④ 抵当権設定登記(ローン利用時)
- タイミング:所有権移転登記と同時または直後。
- 目的:金融機関が融資の担保として土地に抵当権を設定する。
- 注意点:これが完了しないと融資が実行されない。
- 実務:通常は銀行を通して、銀行指定の司法書士が手続きを行う。
⑤ 根抵当権の抹消登記(売主側)
- タイミング:売買契約の直前または同時に行うのが理想。
- 目的:売主が土地に設定していた根抵当権を抹消し、土地を「担保なし」に戻す。
- 注意点:売主が借入を返済し、金融機関の同意が必要。買主の支払代金を使って抹消するケースが多く、司法書士が同席して同時に処理するのが一般的。
⑥ 抵当権抹消登記(買主側・ローン完済後)
- タイミング:ローン完済後。
- 目的:自分が設定した抵当権を抹消し、土地を完全に自由な状態にする。
- 注意点:完済後、金融機関から「抵当権抹消書類」が発行される。それをもとに法務局で登記申請を行う。司法書士に依頼もできるが、自分で申請することも可能。
登記の流れまとめ
土地の購入や住宅ローン利用にあたって、登記にの流れを、時系列でまとめてみます。
| タイミング | 登記内容 | 担当者 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 分譲地開発時 | 分筆登記 | 土地家屋調査士 | 大きな土地を複数に分けて新しい地番を付ける手続き |
| 分譲地開発時 | 表題登記 | 土地家屋調査士 | 分筆された土地ごとに「地積(面積)」「地目(用途)」などを登記簿に記録 |
| 売買契約前〜契約時 | 根抵当権抹消登記 (売主側) | 売主+金融機関+司法書士 | 売主の借入に基づく根抵当権を消して、買主が購入できる状態にする |
| 売買契約後 | 所有権移転登記 (買主側) | 買主+司法書士 | 売主から買主に正式に所有権を移す手続き |
| 売買契約後 | 抵当権設定登記 (買主側) | 買主+金融機関+司法書士 | ローンの担保として、金融機関が土地に抵当権を設定 |
| ローン完済後 | 抵当権抹消登記 (買主側) | 買主+司法書士 買主だけでも可能 | ローンを完済後、抵当権を抹消して土地を自由な状態にする |
【参考】司法書士と土地家屋調査士の違い
- 表題登記と分筆登記 → 土地家屋調査士(表示登記系だから)
- 所有権移転登記・抵当権設定登記 → 司法書士(権利登記系だから)
実務上は、調査士と司法書士が連携して処理するので「全部司法書士がやってくれてる」と誤解されることが多い部分でもあります。
抵当権抹消登記の流れ(ローン完済後)


気が早い話ですが登記の事を調べているうちに気になったので調べました。
私が一番「自分でやる必要がある」と感じたのが、この抵当権抹消登記でした。完済後は銀行がすべて手続きをしてくれるわけではなく、所有者である自分が申請をしなければいけません。
税金と一緒でとる時は自動で処理、受けるときは自分で処理。
受けるときも自動で処理してくれよー😅
話が変わりますが先日、20年前にローンで買った車の車台Noが腐食で見えなくなったので打刻しに行った時、車の所有者がローン会社になっていてびっくりしました。
忘れないように処理しておきましょう😀
① 銀行から必要書類が届く
ローン完済後、銀行から次のような書類が送付されます。
- 抵当権解除証書(または弁済証書)
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報(または登記済証)
- 金融機関の委任状
これらは 抵当権抹消登記に必要な書類一式 です。
② 登記申請は所有者(買主)が行う
銀行は書類を揃えて渡すところまでで、登記申請自体は自分で行う必要があります。
- 自分で法務局に持ち込んで申請する
- 司法書士に依頼する(報酬が発生します)
どちらかを選択できます。
③ 登記簿から抵当権が消えるのは申請後
注意点として、申請をしなければ抵当権は登記簿に残ったまま になります。
そのまま放置すると、将来的に土地を売却したり、再度担保にしたりするときに支障が出る可能性があります。
私自身、ローン完済後にこの抹消登記をどうするか考えなければいけないと知った時は少し驚きました。
銀行が最後までやってくれるわけではないので、「自分でやる」または「司法書士に依頼する」の二択になることを理解しておいたほうが安心だと思います。
建築基準法第22条区域について


私たちの地域は「防火地域」や「準防火地域」ではありませんが、建築基準法第22条区域に指定されていました。
最初に聞いたときは、
「防火扉や防火窓が必要なの?建築費用が高くなるのでは?」
と不安になりました。
しかし、私の地域の場合は 「壁と軒を不燃材にする」 というルールだけで、特別な防火設備までは不要とのことでした。
補足
- 第22条区域とは、火災の延焼を防ぐために外壁や屋根などの仕上げ材に制限がかかる区域のことです。
- 地域によって制限の内容は違います。私の地域のように「不燃材の使用のみ」で済む場合もあれば、もう少し厳しい制限がかかることもあるそうです。
文化財保護法と開発時の調査


契約時に説明があったのが 文化財保護法 です。私の土地は文化財保護区域の外でしたが、それでも分譲地開発の際には「試し掘り」をして調査していたそうです。
もし工事中に遺跡や埋蔵物が出てきた場合は、工事を止めて施主の費用(数千万円)で調査をする義務があるとされています。長引けば数年単位で工事が止まるケースもあるとのこと…。
一応、法律上は「出てきたら申告する」という建前ですが、実際どう運用されているかは…😅
施主としては心配になる部分ですが試し掘りの結果を信用するしかありません。
固定資産税の減税措置について


土地の固定資産税には減税措置があります。
一般的には、土地の引き渡しから翌年1月1日までに建物が完成していれば「住宅用地」として1/6に軽減されます。
私の場合、土地の引き渡しが 2026年4月1日、建物の完成予定が2026年12月31日までなら減税を受けられるのですが、もし2027年にずれ込んだら減税なしで数か月分を払う必要があり、減税有り・無しの差額は約13万円…。かなり心配しました😱
ところが、私の地域では「土地引き渡しから3年以内に建物を建てれば減税措置が適用される」との説明を受けました。これで安心しました😋
補足
- 固定資産税の減税措置は自治体ごとに細かいルールが異なる場合があります。
- 契約前に必ず不動産会社や市役所の税務課で確認した方が良いと思いました。
手付金等保全措置について
契約書を見ると「手付金等保全措置:講じません」にチェックが入っていました。
「え、50万円の手付金が、不動産会社が倒産したら戻ってこないの?」
と不安になりました😥
でも不動産会社は 当然、宅地建物取引業保証協会に加入しています。この協会には保証金制度があり、会社が倒産しても保証を受けられる仕組みがあるそうです。
制度自体は安心ですが、契約書だけ見ると分かりづらかったです。不動産屋も分かりずらい内容だという認識はある様でした。
宅地の契約不適合責任に関する保険について


もう一つ「宅地の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等:講じません」にチェックが入っていました。
これも最初は不安になったのですが、説明を聞くと「これは建物に関する条項で、土地には関係ない」とのことでした。
正直、契約書を初めて読んだときは意味がわからず戸惑いましたが、説明を受けて納得しました😀
特約条項で確認したこと
工事遅延と引き渡し
契約書には「工事の遅延等により引き渡しが遅れる場合があることを買主は了承する」との条項がありました。
遅延に対する不動産屋へのペナルティがなかったので確認したところ、
- 工事完了:2025年12月まで
- 書類作成:2026年2月まで
- 引き渡し予定:2026年4月
と余裕を持ったスケジュールになっていました。本来であれば遅延ペナルティがあると安心ですが、50年続く地元企業で、悪評が立てば存続できないはずの会社なので、そこまで神経質にならずにスルーしました😅
念のため、造成計画表はもらいました。
不安であれば以下の様な条項を契約書に付けてもらう様、交渉すると良いと思います。
数値と期間に関しては自身の事情とその土地の家賃などの相場に合わせて調整するのが良いかと思います。
- 30日以降の遅れに対して、5000円/日の遅延金を払う事
- 1回/週の進捗報告を行う事
- 90日以降の遅れに対しては契約の白紙解除と全額返金
ちなみに私たちの分譲地開発計画の12〜2月の「書類作成期間」は、公図上の「既に存在しない市道」と「新たに造成する開発道路」を、市と不動産会社が交換する手続きに時間がかかるためとのことでした。
開発分譲地ならではの手続きですが今の道路と公図の道路が全く違うという事はよくあるとの事でした。実際、公図を確認しましたが全然今の道路と違い驚きました😮
ゴミ置き場・公園・貯水池の維持管理


当初は「共通設備って清掃や管理が面倒では?」と心配しましたが、次の仕組みがあることがわかりました。
- 不動産会社が管理組合に約10万円を拠出
- 既存33区画の管理組合に今回の14区画が合流
- 年間管理費は 1,000円、そこから清掃会社に委託
今の地域では自治清掃が割と負担になっていました😰
というのも若い世帯に仕事を押し付けてくる傾向があったので、その心配がなく安心しました。
現在私の住んでいる地域の問題点(主に愚痴)はこちら
契約書には「維持管理の義務は代々引き継ぐ」と明記されているので、将来的なトラブル(支払い拒否)も少ないと考えています。
公租公課分担の起算日
前回の記事に「調べたけどよくわからなかった」例として挙げた件になります。
契約書には「公租公課分担の起算日:2025/4/1」と書かれており、引き渡し(2026/4/1)と違うのでは?という疑問を持ちました。
説明では、これは 「固定資産税の評価は年度によって変化しますがその基準年度が2025年度分から」という意味であり、実際に支払うのは引き渡し後からとのこと。
とても紛らわしい書き方でしたが、契約書の別条項にも「引き渡しから買主が分担」と記載があったので納得しました。
これも「わかりずらいですよね」と不動産屋さんは言われていました😅
違約金の額(20%)
契約書には「違約金20%」とありました。宅建協会の標準は10%、最大20%なので、強気の設定だと思いました😮
違約金が発生するのは「売主が契約に着手した時」からとのこと。具体的には司法書士が登記に動いた時点を指すそうです。
未完成の分譲地である私のケースでは、引き渡し直前までは「手付金の放棄」で解約できると不動産屋から聞き、安心しました。過去の判例もそのようになっているそうです。
うーん…とってもわかりずらい😅
境界の明示


契約書には「道路杭の設置を省略」といった不安になる記載はなく、道路側には金属製の赤バッテンの杭を打つ予定とのことでした。
省略となる場合、必要性に応じて杭の施工を依頼しましょう。
所有権移転登記の場所
通常は銀行で、司法書士・売主・買主が集まって行うそうですが、ネット銀行の場合は不動産屋の事務所で手続きするとのことでした。
平日の午前に行うため、有休を取る必要があるので計画的に進めましょう。
引き渡し後の契約不適合責任
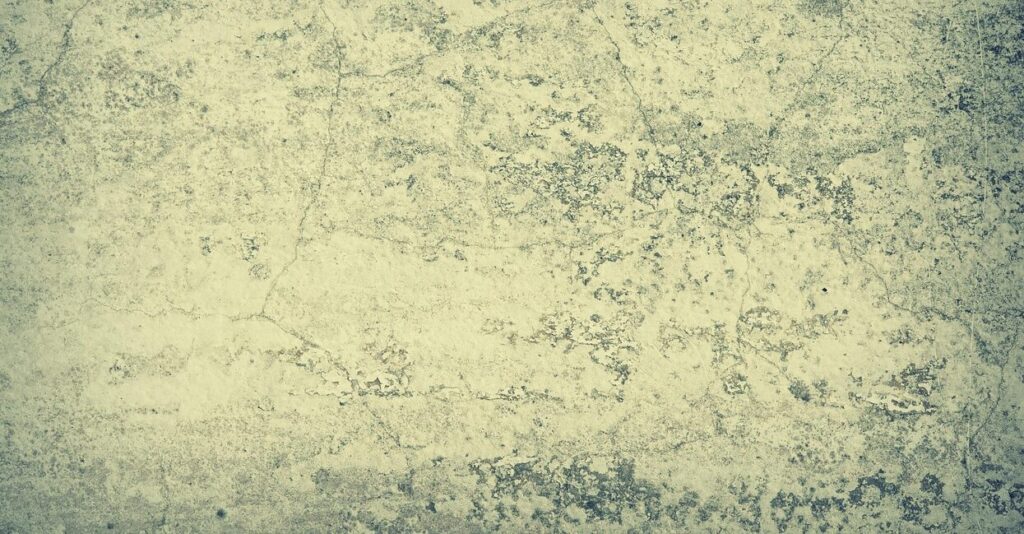
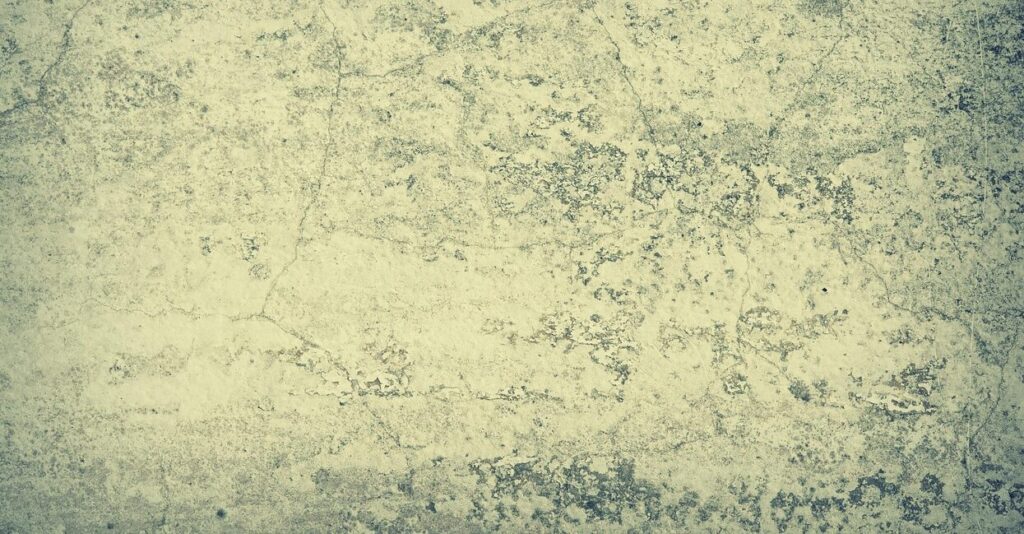
契約書には「社会通念に照らして軽微であることを除き、補修を求められる」とありました。
「軽微ってどの程度?」と質問したところ、
- 擁壁などのひび割れ → 補修対象
- 擁壁等の設置により土地面積がコンマ数㎡ずれる → 誤差として容認
との説明でした。
工務店にも確認したところ「開発許可申請を経て市の検査を受け、検査済証を取得しているので大きな問題はない」とのことでした。
契約確認チェックリスト


今回の確認項目です。
必要なところを抜粋して使ってみて下さい。
契約前に準備しておきたいもの
□ 疑問点は 契約書ではなく重要事項説明書(重説) に書き出しているか
□ 契約の1週間前までに 重説と契約書を受け取っているか
□ ChatGPT等で確認した内容を整理できているか
重説で議論になったポイント
固定資産税について
□ 分譲地特有の共有設備(公園・貯水池等)の 固定資産税はかからない
測量図に関する不安
□ 自分の土地の境界が 確定測量図か地積測量図か を整理
□ 確定測量図が無い場合、隣地の地積測量図を取り寄せて座標を照合
□ 地積測量図の場合、2002年以降の「世界測地系」で作成された物あるか確認
根抵当権の設定について
□ 契約書に「引き渡しまでに抵当権を抹消する」と明記されているか
今後の登記の流れ(①〜⑥)
□ ① 分筆登記
□ ② 表題登記
□ ③ 所有権移転登記
□ ④ 抵当権設定登記
□ ⑤ 根抵当権抹消登記(売主側) → 契約前後に処理されるか確認
□ ⑥ 抵当権抹消登記(買主側) → ローン完済後に自分で対応する
抵当権抹消登記(ローン完済後)
□ 銀行から送付される必要書類(解除証書、登記原因証明情報など)を確認
□ 登記申請を 自分で行うか司法書士に依頼するか を決めているか
□ 申請をしないと抵当権が登記簿に残ることを理解しているか
建築制限(建築基準法第22条区域)
□ 自分の地域が 建築制限区域に該当するか を確認したか
□ 必要な仕様(不燃材の使用など)を理解しているか
文化財保護法と開発調査
□ 工事中に埋蔵物が発見された場合の対応を確認したか
□ 分譲地開発時に「試し掘り」調査がされているか確認したか
固定資産税の減税措置
□ 土地の引き渡しから 建物完成までの期限 を確認したか
□ 自治体ごとのルール(3年以内であれば土地固定資産税減税ルールなど)を確認したか
手付金等保全措置
□ 契約書の「講じません」にチェックが入っていないか確認
□ 宅地建物取引業保証協会の保証金制度などの救済措置を確認
宅地の契約不適合責任に関する保険
□ 「建物のみの」条項であることを理解しているか
特約条項(工事遅延と引き渡し)
□ 引き渡し予定日と工事スケジュールを確認したか
□ 遅延時の補償条項について確認・交渉したか
□ 造成計画表を受け取っているか
ゴミ置き場・公園・貯水池の維持管理
□ 管理組合の体制や年間管理費、清掃方法を確認したか
□ 契約書に「維持管理の義務は代々引き継ぐ」と明記されているか
公租公課分担の起算日
□ 契約書の起算日(例:2025/4/1)は 税の基準年度 であった
□ 実際の支払い開始は 引き渡し後から であることを契約書で確認したか
違約金の額(20%)
□ 契約書の違約金率(標準10%、最大20%)を確認したか
□ 違約金の発生条件を確認したか
□ 未完成分譲地では引き渡し直前まで「手付金放棄」で解約できた
境界の明示
□ 道路杭が省略されず、実際に設置されることを確認したか
□ 設置予定の杭の種類を確認したか
所有権移転登記の実務
□ ネット銀行の場合、不動産会社の事務所で平日午前に行う
□ 手続きに備えて休暇を取得できるように調整したか
引き渡し後の契約不適合(施工不良等)
□ 「軽微」の範囲について不動産会社に確認(擁壁のひび割れなど)
□ 面積の誤差(コンマ数㎡程度)は許容範囲とされる
まとめ
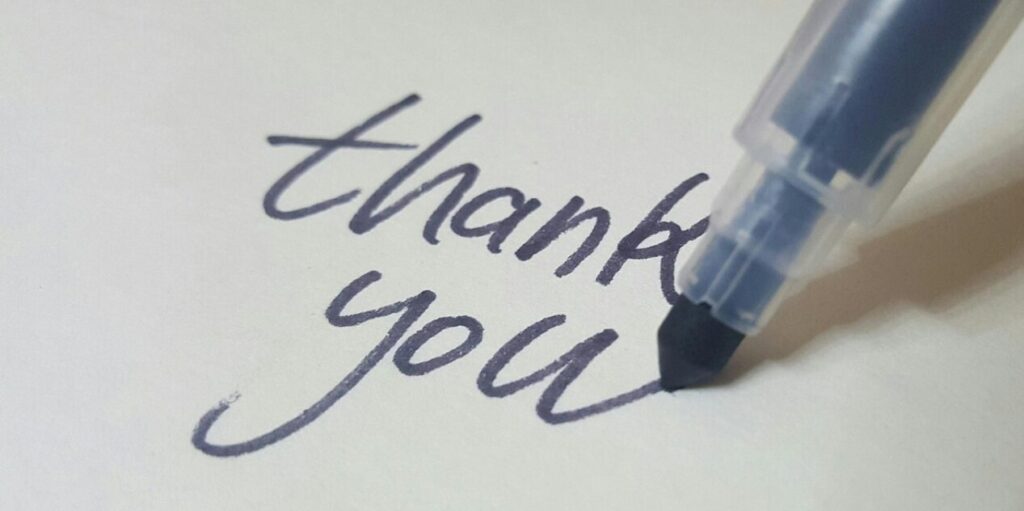
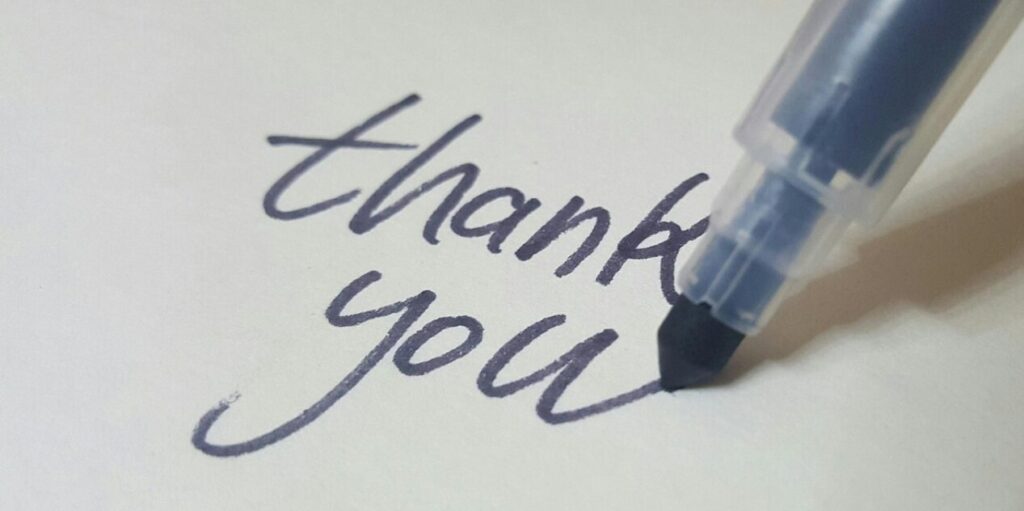
ここまで読んでくださりありがとうございます。
契約書の条文は難解で、読み手にとっては「何を意味しているのか?」と不安になる部分が多いですが、こうして一つずつ疑問を持ち、質問し、整理していくことはとても大切です。
この記事を最後まで読まれたあなたは、細部まで理解しようとする真剣さと、将来のトラブルを防ぐ力を既に持っています。
ぜひその姿勢を大切にしながら、不安を一つずつクリアにして、安心できる不動産取引につなげていってくださいね。
今後も役に立つ情報を発信していきますのでブラウザのお気に入り登録よろしくお願いします😀
追記:初めてNote有料記事を作りました。
一条工務店にご興味がある方は覗いてみて下さい😀
Withdom建築設計についても坪単価、財務状況、性能、建材に関する事をまとめましたのでこちらもよろしくお願いします😄
本気で探すHM|Withdom建築設計への訪問|14の質問への回答と財務状況の分析